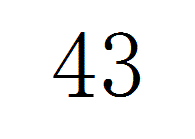 |
|
空間から切り離された月明かりだけが、妙に冴え冴えしかった。 駆け抜ける冷気、吹き抜ける風が陽子の髪をすくって目の前に紗をかけていく。自身の赤い髪を透かした、向こう側にいる青年を陽子はただ呆然と見つめる。右頬からは生ぬるい筋がいくつも垂れてきて、滑り落ちる赤の雫は、じっとりと首筋の衣に吸い込まれていった。何もかもが暗い中、視界の中で翻る金の波だけが、まばゆい。 呆然と立ちすくむ陽子。一方景麒は、主人の姿を目にいれながら、声はおろか、自身の意思で身体を動かすことさえ出来なかった。景麒を額を焼く灼熱の感覚が襲う。麒麟の本性が否定する、凶器を向けるだけで、景麒は腹の奥から吐き気が込み上がってくるのを感じる。 (主…上…) 身体が熱い、それなのに酷い悪寒が景麒の背筋を駆け抜けていった。まともに立てるかどうかも危うい状態にも関わらず、はたから見た自分は、涼しい顔をして、鏃の標準をきりりと陽子に定めている事は景麒にとって酷く滑稽なように思われた。透明な硝子玉に似た瞳に、景麒の一切の感情は映っていない。 景麒はひとりでに動く体の中、必死に陽子に呼びかけた。 (主上…お逃げ…下さい…) 指先に意図せず力が籠もり始める。腕がゆっくりと、弓を後ろに引き出したのを、景麒は感じた。景麒の中で恐怖が音を立てて渦を巻き、彼の唇から音が漏れた。 (景麒‥) 唖然としていた陽子だが、弓を引く指先が細かく震えていることに、その時気がつく。何の表情もない顔から細かな汗が噴き出して、彼の輪郭を滑り落ちていった。 「景麒…お前…」 景麒の唇から微かな音が出る。 「しゅ‥じょう…お逃げ、く、だ…さい」 「景麒…!」 彼はその掠れて形にならない言葉を飲み込んで、なんとか声を絞り出した。陽子の耳に届いたのは、それは声と呼んでも良いのかと躊躇われるほど――あまりにか弱い音だった。 「身体が…私の意思では…動かせ、ませ…ん。どうか‥」 景麒が言い終える前に、陽子はさっと彼の額に目を凝らす。角が在る筈のそこには何か赤く書きなぐられたような痕があった。それは白い景麒の顔にはあまりに痛々しく浮いている。震えながら、仁の本性に逆らった武器を持たされた景麒を見た瞬間―――陽子の中で怒りの炎が巻き上がった。陽子が理解した景麒の現状――― 景麒は角を支配され、身体を乗っ取られている。 現状を理解した陽子の脳裏に、いやらしい笑みを浮かべた髭面の男の顔が―過ぎった。 「あの、男か…。あの、逆賊の――仕業か‥!!!」 低い声が、怒りを孕んでその場に響いた。眉間に濃く畳まれる皺、陽子の翡翠の瞳が燃え上がる。景麒は震えながら、弓矢を構え、なんとか声を絞り出す。 「お‥願いです‥私を捨ておいて、お逃げ‥くだ‥さい…どうか…!」 陽子は何も答えない。答えないまま、鋭い眼光で、じっと景麒を見据えていた。 景麒は自分の指先に冷や汗が浮き始めたのを感じながら、乾いた唇を湿らせる。闇の中、体全体が…震え始めた。 「しゅ‥じょ…う」 どうか、逃げてくれ 景麒が泣きたいくらいに望んでいるのは、その一点だけだった。 主の頬を滑っていく赤の筋が景麒の心を引き裂いて、指を震わせていく。こちらを真摯な顔で見つめる陽子の姿が景麒の胸を焼いていた。そして同時に、景麒の目に映る景色の中で、弓矢の先の鈍い鋭さはぴったり陽子と重なりあって景麒を嘲笑う。顔立ちだけが平然と無表情な中で、景麒の声に――涙が混ざった。 「お願いで‥す‥逃げて…下さ‥い」 指先にぐっと力が籠もる。貯められた力が爆発する時を秒読みで待っているようだった。腕の筋肉が震えだし、景麒は掠れる声で、懇願した。 「しゅ‥じょう‥!」 指先から弓矢がずるずると逃げ始める。 景麒が陽子に逃げるよう願ったその時、陽子は力を込めて‥叫んだ。 「そんなこと、出来るわけ、無いだろう!!!!」 「…!!」 叫んだ陽子目がけて、弓矢が唸りをあげ、空中に飛び出した。 目を見開く景麒の目の前で、恐ろしい速度で陽子目がけて駈け出した弓の軌跡と、紅が闇の中で翻る。陽子は水禺刀を掴み、身を捩って弓を避け、景麒目がけて‥飛んだ。 景麒の腕は彼の意思を無視して動き出し、背中の弓に再び手を伸ばす。空中に浮いた陽子に向かって、景麒の身体は再び、彼女の身体に標準を合わせた。景麒の顔が汗を吹き出して、歪む。空中で陽子の逃げ場などどこにもなかった。 「主上…!!」 陽子が見たのは今度こそ陽子に突き刺さろうと嘲笑う鈍色の鏃だった。空中での逃げ場は無い。陽子はしっかりと目を見開いたまま、力を込めて駆け出そうとする鏃を‥見つめる。景麒の漏れる悲鳴が聞こえた。 「主上…!!!」 時間がゆっくりと、音を無くして流れ始めた。 空気を裂いてこちら目がけて駆けてくる凶器、ゆっくりと瞬きする自身の睫毛、景麒の必死の声が、遠い。 避けられない、と陽子の直感が―叫ぶ。その場で切り取られたように浮かぶ陽子の身体と、唸りを上げる弓の鏃、その二つの接触が迫る。 だが、何もかもが色褪せて見えたその時、弓矢が刺さる前に陽子の身体を衝撃が襲った。強い衝撃が頭を襲い、一瞬視界が暗くなった。 (え…?!) 誰かに体を引かれる浮遊感だった。本当なら有り得ない、重力を無視して、誰かの手で空中から身体が引きずり降ろされるのを、陽子は流れる空気から感じた。かろうじて見えたの光景は、陽子の目の前を、景麒の放った弓が流れていく瞬間だけだった。陽子が見たのは、それだけだった。 音が消え去ったその空間、陽子は、誰かの荒いと息を…聞いた気がした。 一瞬にも思える音のない滞空時間の後、気がついた時には陽子は地面に身体を打ち付けていた。 「くっ…!」 衝撃で目が眩み、陽子は地面で咳き込んだ。ぐらりと視界が揺れ、数秒後に鈍い痛みと共に、陽子の世界に急速に音が押し寄せてくる。どこどこと心臓が鳴ってうるさい。覚悟したはずの矢は刺さっていない、手探りで自身の体を確認した陽子は、かすむ視界で周囲を見渡す。 だが、その時にはもう、陽子の周囲に景麒以外の人影など、陽子の目では確認できなかった。 (何…だったんだ…?何故、助かった‥?) 確認できるのは、ただただ無事な自分の体と、あらぬ方へ飛んだ弓矢だけだった。地面に倒れたまま、陽子は荒い息で胸に手を当て、自身に起こった事が分からず、目を瞬く。 だが、細かく詮索する時間は、今の陽子には残されていなかった。 一瞬呆然とした陽子の背後で、きりりと弓の引き絞られる音がして、陽子ははっと振り向く。見れば、身体を乗っ取られた景麒が新たな弓矢に指をかけていた。 「景麒…!」 砂煙を上げ、陽子は景麒に向き直り、再び弓を構えようと動き始める景麒の懐目がけて、低く駆け込んだ。手刀で景麒の弓矢をはたき落とし、景麒が腰から抜いた刀の刃先を陽子は水禺刀ではじき飛ばす。 (今、助ける…!) 陽子は後ろに飛びすさぶ。 だが次の瞬間、自身の目の当たりにした光景に彼女の息が止まる。 陽子が見たもの…それは操られる景麒は震える手で、懐から取り出した短剣を、自分の喉元に突き立てようとした光景だった。 景麒の喉元に振り下ろされる鋭利な輝きに―― 陽子の世界が、白く、焼かれる。 「やめろおぉ!!」 陽子は叫びながら、水禺刀を投げ出して、剥き出しの刃先に向かって手を伸ばす。まるで噛み付くように、景麒の喉元に突き刺さる直前に、陽子の掌が短く鋭利な白銀を掴んだ。 「う…!!」 刃先が、止まる。止まったその瞬間、白い輝きを透明な赤の雫が滑っていく。灼熱の痛みが掌を焼き、陽子は苦悶の表情を浮かべた。 「あぁっ‥!!」 「主…上…!!!」 その瞬間景麒の動きが止まり…陽子は景麒の手から短剣を投げ捨てる。景麒は歪む視界の中、涙を浮かべて自分を見つめる陽子の表情を捉えた。陽子はふらりと彷徨うように景麒の方へ手を伸ばす。 (主上…) ぐらり と蹌踉めく景麒の身体を、陽子は――強く‥抱きしめた。 ::::: 無音が静かにその場に降り落ちる。景麒を抱えたまま、二人は荒い呼吸でしばらくその場で動きを止めていた。やがて、静寂の中、景麒が僅かにみじろぎする。 「主‥上…」 「景麒…!」 見れば、息も絶え絶えに陽子を見上げる景麒の額の赤の文字が、先程の衝撃で僅かに掠れていた。陽子は懐から碧双珠を取り出し、そっと景麒の額に当ててやる。とろりとした珠がほんのりと輝いて、彼の額に刻まれていた文字を拭い去った。 「景麒…良かった…」 陽子はほっと目元を緩める。疲れきっているのか、景麒は弱々しく頭を振ってじっと陽子を見上げた。疲労が現れたその顔に、陽子は辛そうな表情を浮かべ、景麒に向かって囁く。 沈痛で優しい―声だった。 「すまなかった…私が不甲斐ないばかりに、麒麟のお前がこんなことをさせられるなんて…。長い間留守にして…すまなかった」 景麒は陽子を見たまま、今度は強く首を振る。陽子は少しだけ苦々しく口元に笑みを浮かべ、彼の金糸をそっとすいた。 「私は‥一度何もかも、失くした。命以外、本当に‥全てを。自分自身さえも…私は失くした」 口の中に酸味が走り、陽子の中を記憶の渦が駆け巡る。景麒が眉を寄せるのを見ながら、記憶の全ての出来事をなぞり陽子はふっと頬を緩くほどく。 「でもね、私は今回の旅で、何が本当に大切なのか、この目でその鱗片を‥見れた気がするんだ」 弱きを支配しようとする人間の本性、闇と光を併せ持つ自分自身の姿、規律に縛られず、心に従うことの出来る強く優しい人々を、陽子はその目でしかと見た。 分かった大切なことと、今なお分からず胸の奥で渦巻くこと、その全てが絡みあって、自分自身が形成されていることを、陽子は肌で実感したのだ。 分からないことは陽子にとって山のように存在する。陽子は苦笑を漏らす。 ふと、先程の不思議な体験が頭をよぎり、陽子は眉をひそめた。 自分が叩きつけられた地面を見るが、先程何が起こったのか、陽子には未だに分からない。 陽子はそっと景麒に視線を落とす。 「置き去りにして、悪かった。お前には迷惑をかけ…っ、うわ?!」 途中、陽子の言葉が途切れた。 (な…?) 驚いたまま固まる陽子。何かがふわりと陽子の鼻をくすぐる。 次の瞬間陽子が見ていたのは、景麒の胸元の袍の布だった。わけが分からず‥陽子はゆるりと一度だけ瞬きをする。頬に触れる柔らかな絹の感触、薄い布を通して伝わる熱、固い胸板の感触に、陽子の時間が止まる。気がつけば―― 陽子は固く景麒に抱きしめられていた。 陽子が抱きしめた以上に―固く強く、抱きしめられていた。 景麒の鼓動が布を通して聞こえ、景麒の身体から僅かに伝わってくる震えに、陽子はおずおずと顔を上げる。 そこには唇を噛み締め、溢れだす感情の波に耐えるような‥景麒の顔があった。震える景麒の声がして、陽子は驚いたまま、景麒の腕の中で固まる。景麒は押し出すように一つ一つの言葉を陽子に渡す。深い深い後悔を、陽子はその時、景麒の言葉の中に見た。 「申し訳…ございませんでした…。主上は‥主上には何一つとして非は御座いません…。至らないのは私の方だったのです」 陽子の顔は驚いたまま‥景麒の顔を見つめていた。普段無表情の景麒の肩が萎れていることに、陽子は気が付く。 「景麒…」 草の音だけが、静かに揺れる。景麒は肩を震わせながら、精一杯胸に詰まった言葉を絞り出した。 「申し訳ありません。麒麟とは名ばかり…私は主上の心情も察知せず、浅はかな発言で貴方を傷つけました‥。どれだけ正論を貫き通しても、そんな私が、どうして貴方の半身だなんて、胸を張って言えるでしょう。今回の不祥事の原因の一端は私にあります。主上には多大なるご迷惑をお掛けしました…」 陽子は息を呑んで景麒を見上げる。それは本当に、陽子が景麒から初めて聞いた、心のこもった謝罪だった。景麒は辛そうに顔を歪めたまま、項垂れて陽子に囁く。 「お許し下さい…。ですが、どうか、主上がよろしいと仰るのならば、どうか…私の言葉を、聞いては下さいませんか」 景麒はじっと陽子を見つめた。自分の中で、ずっとずっと心の奥底に灯していた感情の炎が景麒の胸を焦がす。 景麒の言葉に、陽子は驚いて景麒を見るが、やがて小さく頷いた。 彼は震えながら、唇を噛みしめる。声を押し出そうとした途端、心臓が早鐘のように打ち始める。 それは、熱くて、痛くて、苦しくて、どうしようもないくらい大切な感情だった。 (主上…) だが陽子を腕の中に感じながら、ずっとずっと言いたかった言葉を、景麒はそれ以上口にする事が出来なかった。 思えば、自分はいつもそうだ。昔も、今も、自分たちが記憶を奪われたあの時も。 胸にあって焼き焦げるような熱さが喉を焼くのを感じながら、どうして、と景麒は思う。 どうして、主人を説教する時には口があれ程回るのに、一番大切な、たった一言を口にだすことが出来ないのだろう。 たった、たった一言。 心配してても、怒っても、喧嘩をしても、その一言さえ言えればよかったのに。 そうしたら、ほつれた結び目だって結び直せるのに。強く太く、結び直すことが出来るのに。そこから新しい何かが、きっと始まったのに。 難しくもない、堅苦しくもない、その言葉がどうして、自分は―――言えなかったのだろう。 堅苦しくて、小難しい事はいくらでも並べ立てることが出来るのに、肝心で、簡単で一番大切な一言は…言えもしない。 景麒は自身の想いの強さに、強く瞑目して嗚咽を漏らす。耳元で心配するような優しい、声がした。 「景麒…」 言葉が出てこない景麒が目を開けば、美しい少女の姿が目に入った。 それは強くて、優しい景麒の唯一人の大切な人で、口の中で止まった言葉が滑りだすにはその姿だけで十分だった。 景麒の顔がわずかに歪み、唇から想いが―零れる。 愛しています という言葉が響いた。 「お慕い申しております。貴方のことを、誰よりも…。主上のそばにいることが出来る、それが私がここにいる意味なのです。それが、私の生きている…意味なのです。どうかおそばに、置いて下さい」 月明かりの中、空高い天空に近い場所なのに、何故か穏やかな潮騒の臭いがした。その瞬間、景麒が陽子に己を打ち明けることになったのは、偶然なのだろうか。陽子の胸が熱く詰まって、声が漏れなかったのは…景麒の想いにすぐに言葉が出なかったのは偶然なのだろうか。 陽子はじっと真摯に景麒の顔を見つめる。 「景…麒」 想いには想いが返される。 胸が、頭が、身体が、何もかもが熱かった。頑なだった心が融け合い、お互いの確認できなかったその本質に触れ合える機会を、果たして人はどれほど持っているのだろう。 温かい感触を感じながら、陽子は景麒の身体に――腕を回す。 その瞬間低い月明かりの中、景麒と陽子の伸びた影が遠くで重なって揺れていた。 |
| back index next |