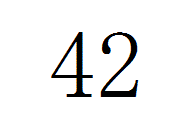 |
|
目から透明な雫が盛り上がって、視界を溶かしていく。零れていく大粒の雫を、陽子は嗚咽混じりに、乱暴なしぐさで拭った。強く唇を噛みしめた陽子の中から声がする。 「主上…」 「大丈‥夫だ」 陽子は涙を指ですくいながら、答えた。噛み締めた唇の隙間から、冗祐、と彼女の下僕に呼びかける。 「お前は‥まだ私に付いてきてくれるか。何もかもを奪われた、お前に助けてもらってばかりの至らない私に。大切なものを取り返す、手助けをしてくれるか」 冗祐が小さく笑う気配がした。 「私をそこまで買って頂けているのですか。私にとって従うべき主は初めから明確…。貴方以外にはおられないのです。先代の王、貴方、二人の王に付き従いましたが、私を受け入れた王者は唯一人…貴方だけです。私にとっての真の主人は…貴方です」 言葉をつぐむ陽子の中で、冗祐が動く。それはまるで陽子に対して 「従いましょう、どこまでも。この命尽きるまで、私は景王君にお仕えいたします」 ありがとう と陽子は少しだけ笑う。視線上にある月は、もうかなり地面に近くなっている。身体に力が戻り始めて、陽子は腕に力を込めた。行こう と陽子は雲の上を見つめる。さっきまであれ程近かったのに、果てしなく遠くて、自分の足でたどり着けるかも分からないくらいに霞んで見える場所だった。陽子は悔しさに唇を噛みしめる。 その時―― 冗祐が動き、立ち上がろうとした時、陽子は金色の光を視界の端に見た気がした。陽子の瞳の中で輝く、空に浮かぶ、小さな光の (…?) 目を細めれば、それは優美な獣のように見えた。空を駆ける、四股の獣。美しいのに―速い。こちらに向けて駆けてくる動きが、先程自分を乗せた獣の動きとぴったり重なり、陽子は思わず言葉を失う。濃い金の 明るい少年の声が響き渡った。 「陽子!!!見つけたぞ!!!」 すっかり見慣れたその姿を見て、陽子は叫んだ。 「延台輔!!」 身体を起こす陽子。彼女の目の前で、優雅に舞い降りたそれは――隣国の麒麟だった。 「良かった…!落っことしちまった時は焦ったけどな。やっぱり陽子は無事だったか!」 陽子は目を瞬く。 「じゃあ…吹き飛ばされた時助けてくれたのは、やっぱり…」 六太はふふんと陽子に胸を張る。 「そ。俺!あそこで間に合って良かった。雲海を突き抜けたあの高さから落ちたら、仙とも言えど危なかったからな‥。まあ結果的に落としちまったけど…それは悪かったよ。無事でよかった」 「ありがとう…。延台輔は、何故ここに?」 六太の顔に渋いものが走る。 「本当は尚隆から『俺が動けるようになるまで慶に入るな』って言われてたんだけどさ、陽子のことも気になったし、あいつも最近様子がおかしかったから、尚隆が慶に入った瞬間から、使令を使ってずっと様子をうかがってたんだ」 「そう…だったの」 六太は大げさに息を吐いて肩を竦めてみせた。 「尚隆は自分が動けるようになるまで俺に来るなって言った。だけどさっき、陽子が尚隆を正気に戻してくれたから、あいつはもう自由に動ける。景麒も奪われている陽子は危険な状況だったから、特急でここまで駆けてきたんだ。なんとかギリギリ役に立ったか?」 「ああ…!」 六太は満足そうに、そっか と笑った。陽子もつられて笑う。静けさの中笑ったその時、胸に景麒の顔が浮かんだ。 (景麒…) 陽子は雲海の上にある金波宮を見ながら、目の前の麒麟の目線まで屈む。 「延台輔…もし良かったら、もう一つ、私の頼みを聞いてはくれないだろうか」 「何でも言ってみな!」 すっと陽子の眼差しが真剣味を帯びて、六太を見つめる。 「私を…金波宮へ、景麒の元まで、連れて行ってはくれるか。血臭がしたら、無理せず下ろしてくれて構わない、六太くんが良ければ、お願いされてくれないか」 陽子は真剣に六太を見つめる。 泉の水面が 今にも落ちそうな月影が鬣を淡く染める中、六太は陽子を見上げ――そして明るく笑った。 「お安い御用さ!」 ::::: 雲海を突き抜け、吹き付ける突風に陽子は目を細める。風を切る、とはこういうことを言うのだろうか。跳躍する麒麟の筋肉を感じながら、陽子は落ちないよう、延麒にまたがる太ももに力を込める。 くぐり抜ける雲の水。遥か上空に舞い上がり、見えた微かな光に、陽子は小さく息を飲んだ。 「‥見えた!」 「着いたみたいだな…」 とっぷりと闇に浸かった視界に佇む金波宮は、いくつもの淡い光の粒を吹きつけたようだった。光を何度も吹きつけたような場所もあれば、一度だけ吹きかけたように、薄暗い場所もある。明度が高いもの、低いもの、その全てが寄り添って、幻想的な風光を陽子の目の前に創り出していた。翡翠の瞳の表面に、幾千もの光の粒が揺れる。陽子は彩度の違う光を瞳に映しながら、唇を噛みしめた。 (景麒…!) 金波宮に向かって駆けながら、六太が陽子を振り返る。麒麟の脚力が手伝って、先程まで霞んでいた光は急速に強く大きく目の前に広がって、陽子達を包み込む。金波宮の全映が浮かび、気がつけば陽子達はその上空にいた。六太は高度を下げていく。 「陽子…!」 「大丈夫だ…」 迫りくる地面を見つめながら、陽子は囁いた。灯された光を斑に弾いた紅の髪が 「ここまで連れてきてくれて‥ありがとう。もう、私は行く」 「え…?よ、陽子?!」 駆ける六太が目を瞬く。その瞬間、背中が急に軽くなって六太は驚く。陽子が飛び降りた、と理解したその瞬間、麒麟の深く鮮やかな紫眸が見たものは、風に揉まれる赤の波だった。 「陽子!!」 六太の声が響き渡る。落下しながら、声に釣られるようにして陽子が上空を振り仰いだ。陽子は六太に向かって叫ぶ。 「延王に宜しく!!送ってくれてありがとう…私…!」 「…?」 張り詰めていた様に見えた陽子の顔がくしゃりと破顔する。どれだけの困難が、不安があっても笑う強さを、六太はその時目の前で見た。 「頑張るから…!!」 声が響き渡る。 「…!!」 目を見開いた六太の前から陽子の姿が消えて行く。陽子の姿は重力に攫われ小さく消えていく。彼が言葉を返す間もなく地面に降り立った、やっと確認できる程の大きさの陽子は、一度だけ手を振ってその場から駈けて行った。 (陽子…) 六太は何も言わずに風に撫でられながら、無言でその場に浮く。消えていく陽子の背を目で追う中、どこからともなく、彼の使令の声がした。 「景王陛下を…ご助力なさらなくて…よろしいので?」 六太は何も応えない。少しの間黙っていたが、やがて小さく首を振った。 「あいつなら‥自分でなんとかする。あいつには俺じゃなくて、景麒がいる」 「そう…ですか」 手を出してはいけない と彼の中の何かが直感として告げていた。風がざわめく中、それに…と延麒は視線をついと上げる。目の前で揺らめく灯火に目を細めて、彼は雲海へと視線を投げた。 「今は、他にやらなくちゃいけないことがあるだろう。抑えなきゃならねぇ奴がいるってことを忘れちゃなんねぇんだ。尚隆と連絡を取って、俺たちのやることをやろう。それがこの国に還元される筈だ。それに…」 「それに…?」 六太はふんと鼻の穴を広げてみせた。荒い息をそこから吐き出す。 「俺はあのおっさんを一発ひっぱたいてやらなきゃ、気がすまねぇよ!」 使令達が笑う気配がした。六太はにっと不敵な笑みを浮かべ、強く空を蹴って舞い上がる。地上を見つめる六太は、駆け抜ける一瞬前に…陽子が駈けていった方向を振り向いた。 (頑張れよ…陽子) 心で小さくつぶやく激励は、誰の耳にも聞こえない。それでも強く噛み締めて、六太は視線を戻し駈け出した。急速に引きちぎられていく景色の切れ端を尻目に、地上目がけて、六太は全力で駈け抜ける。 その時、夜空を弾く六太の金色の輝きは、地上に落ちていく流星のようだった。 ::::: 「景麒!!…景麒!!!」 陽子は叫びながら、金波宮の内部を駆け抜ける。普段なら兵卒で溢れている筈の場内は、人の気配一つしない。その事実が不気味に陽子に忍び寄り、陽子は思わず眉根を寄せる。 (何故…人がいない…?) 「景麒!!」 声だけが虚しく反響していく。柔らかい唇を噛んで陽子は額に浮いた汗を袖で拭った。視線を走らせても、周囲の気配を探っても、そこにあるのは「無」だけのように思えた。 (どこだ…?) ふと、物音が彼女の耳を掠る。はっとして、陽子はそちらの方を振り返った。顔が輝き、陽子の口から声が漏れる。 「景…」 背後に顔を捻る陽子、その瞬間…白い閃光のようなものが、陽子の側を駆け抜けた。 同時に、彼女の右頬に白熱したものが走り、陽子は衝撃に、目を見開く。 一瞬世界の――時間が止まった。 「?!!」 突然のことに訳がわからず、陽子は呆然と瞬きする。色褪せた陽子の視界の、目の前に壁に刺さっているのは一本の弓矢だった。 「え…?」 壁に深々と突き刺さる弓は、衝撃が抜けきらず、まだ細かく震えている。 弓矢が頬を掠めたと気がついた、その時になって初めて‥鋭い痛みが熱とともに――陽子の頬を焼いた。 「っ…!!」 (何者…?!) 敵か、と陽子は弓が飛んできた方に向かって視線を鋭くして振り返る。身体が瞬時に戦闘態勢に切り替わり、冗祐がぞろりと蠢き、水禺刀を抜き放つ。 一瞬の間が、生まれた。葉のざわめく音だけが響きわたって、耳元を撫でて流れていく。陽子は薄暗く見え始めた人影に目を細める。淡い光が、降り落ち、人影に輪郭を持たせていく。 陽子の瞳が――見開いた。 「え……?」 白刃が光の筋を帯びたその時、弓矢を構えている人影に‥陽子は雷に打たれたように動きを止めた。 陽子の瞳がこれまでに無いほど、大きく見開かれて、止まる。衝撃で開いた唇からは、声はおろか、音さえも零れはしなかった。 水禺刀が震え、陽子の指から滑り落ちる。金属の透明な音が響き渡り、地平線に落ちかけた月明かりだけが弱い光を投げて、視界を澄み渡らせていく。 静謐な空間に風だけが緩急をつけて吹き抜ける。その風の中、弓矢を構えて佇む――人影。月明かりと同じ色の、美しい光輝を帯びた金の波、こちらを見つめる深い深い紫の双眸に陽子は息が止まった。 「景…麒……?」 落ちた言葉を拾うものなど、誰もいない。背の高いその姿に光が落ちて、彼の白金を、美しい無表情の顔立ちを照らしだす。弓矢の先の そこで弓を向けていたのは…人を傷つけられるはずのない、彼女の唯一無二の――半身だった。 |
| back index next |