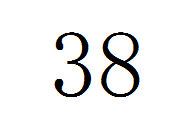 |
|
風が吹き抜けて‥眼の前の少女の髪を揺らしていった。 こちらをゆっくりと振り向く赤の髪の少女。吹き揺らされた髪が彼女の顔に紗を掛ける。だが、それを透かして見える瞳の美しさは、零れた髪の線が掛かっても少しも曇ることは無かった。 息も出来ないまま、浩瀚はただただその場に立ち尽くす。月影を浴びる紅の髪、健康的な褐色の肌。何もかもが美しい、だけどやはり… 何よりも目が離せないのは…鮮やかな彼女の双眸だった。 深く鮮やかなその瞳に、吸い込まれたその時、浩瀚は自身の内部で何かが疼くのを感じた。自身の中に広がるそれはまるで―円を描く、波紋。 「…?!」 頭を抑え、彼は思わず後ろにたたらを踏んだ。少女は不思議そうな顔をしたまま、浩瀚をじっと見つめる。瞳の穏やかさと強さと深さに揺さぶられて、浩瀚は自分が掻き乱されていく感触を感じた。 (何…なんだ‥!) 何かが揺らぎ、浩瀚の記憶を押し開けていく。 「ぐ…っ」 こじ開けられるのは自身の核心部だ。蓋をされ、凍らされていた記憶が煮立ち始め、彼は思わず頭を押さえて膝を折った。全てが目まぐるしく脳裏で渦を巻く。 暗かった脳裏に、唐突に赤が―過る。 「う…あ…!」 「?!おい…!」 少女が驚いてこちらに駆け寄ろうとする。浩瀚は咄嗟に手を出して、少女の動きを止めさせた。なぜ自分がそうしたのか分からないまま、彼は膝を地面について頭を抱える。真紅の少女は明らかに驚いて、心配そうに顔を曇らせた。 「ぐ…あぁ!!」 先程の赤が濃さを増して、浩瀚の瞼の裏に浮かび上がった。 胸が疼く。 強く瞠目したその瞬間、浩瀚の耳元に、聞き覚えのない爽やかな明るい声がした。 『浩瀚!!』 (…?!) 誰だ。 目の前が、白く染まった。彼がゆるりと瞬きした次の瞬間、声が―溢れる。 彼の世界に―光が溢れた。 『私は貴方のことを誤解していたようだ』 『もし貴方が良ければ‥この国の冢宰の位についてはくれないか』 『私はまだまだ至らない…お前は本当に有能で見習わせてもらっている‥。こんな私だが‥よろしく頼む。いつもありがとう』 『浩瀚、お前は‥私に付いて来てくれるのか』 脳裏に走馬灯のように記憶が流れていく。遠くで自分の是という声が聞こえた時、目の前のその人が、嬉しそうにはにかむ気配がした。 驚いて硬直する浩瀚の耳元で…声がした。 『この国にとって、お前にとって、私は‥良い王であることは出来ているだろうか…?』 目を見開いた彼の脳裏に吹き出し始める、今まで忘れていた全ての事実。自身の呼吸の音さえも消えた世界、自分が忘れてはならなかった「その人」の声だけが彼を満たしていく。 目の前に在った紅が、ふとこちらを振り返った。褐色の肌に、美しい瞳の少女が浩瀚を振り向いて笑った。それは柔らかくも、強さを兼ね備えた―優しい笑顔だった。彼にとって唯一無二の、彼がただ一人主と認めたその人の笑顔とでも言うのか。 心の中で一つの単語が滲んだ。 ―主上 「う、あぁあ!!」 頭を押さえて叫ぶ浩瀚。 吹き出した記憶と、脳裏で笑う少女と、目の前で必死の表情を浮かべる少女、全てが重なって――揺れる。 (主…上…!!) 明度も彩度も鮮やかに、着彩されていく記憶の渦の中、彼は自分の主の姿をはっきりと認識した。そしてその時、同時に 「くっ‥?!」 「しっかりしろ!!大丈夫か?!!」 窓際から今度こそ陽子は力を込めて飛ぼうとする。全てを思い出し、浩瀚は目を見開いた。そして、その時、衝立に人影が浮かんだのは同時だった。背後からした物音に、浩瀚は勢い良く振り返る。背後に、もはや見慣れた人影が立っていることに…彼はその時気がついた。その人物を見た瞬間、陽子の顔に衝撃が走る。 背後に佇んでいたのは、背の高い、艷めく黒髪を括り上げた、女顔の残忍な一人の武人だった。 「…!!」 浩瀚の血が凍る。 (なぜ‥ここに…!) 彼の記憶が逆巻いて、楓椿に関する情報が頭を駆けると同時に、先程廊下で対峙した漢轍の狂気に染まった瞳が浮かぶ。 いつ現れたのか、先程王宮に戻ったばかりの彼が見上げる武人―楓椿は、浩瀚の事など見向きもしていなかった。陽子の表情が殺気立つ。 「お前は…!!」 椿楓の口元の弧が鋭く釣り上がる。陽子の手が、刀の柄に滑る。 浩瀚の血が凍り、彼の頭が動く前に、身体が動き出すのを感じながら、彼は自分が力の限り叫ぶのを聞いた。 「お逃げ下さい、主上!!!」 え と目を見開いて、陽子は驚いて動きを止める。楓椿がこちらを振り返ったその瞬間、浩瀚は楓椿を力の限りその場に押し倒し、馬乗りになって羽交い締めにする。押し倒された楓椿は藻掻きながら、浩瀚を鬼のような形相で叫んだ。 「?!浩瀚!!貴様、何の真似だ!!!」 その声に、浩瀚も力の限り楓椿を押さえながら、叫んだ。 「なぜ、お前がここにいる!?」 「彼女がここに来ることなど分かっていた…やっとお会いできた所を、貴様!!!邪魔をするな!!!」 暴れる楓椿をなんとか押さえながら、額に汗を浮かせて、浩瀚は陽子を振り返る。 この男は、危険だということを浩瀚は既に熟知していた。 「お逃げ下さい、主上!!早くここから、逃げるのです!!」 「貴方…」 「申し訳ございません…!私としたことが、多大なるご迷惑をお掛けしました…!台輔の御身が危ない…!!どうか、台輔をお助け下さい!!!」 「台輔」その単語に驚いたまま硬直する陽子。主の顔を見ながら、楓椿の暴れる力が強くなっていく。腕の痺れと、対立する力の強さを、浩瀚は直に実感した。唇を噛み締めて、彼は陽子を見つめる。 陽子との再会の 「放せぇえ!!こうかぁぁん!!」 「っ…!主上、お早く!!貴方にしか、この国を救えないのです!今のこの国の状況を、折り入ってご説明したい所だが、その時間は無い…!とにかく、台輔を…!台輔を、お救い下さい!!逆賊の手がこの国の麒麟に伸びているのです!!」 浩瀚の声を聞きながら、陽子の息が止まる。 「でも…!」 一瞬、陽子は外に視線を投げた。 (早く…!) 浩瀚は腕の痺れを感じながら、荒れた呼吸の中、更に楓椿を男の腕力で締めあげる。 楓椿を抑える浩瀚の手の平が汗で滑り始める。 口はまるで饒舌なのに、これは完全に得意分野外だ と浩瀚は小さく舌打ちをする。桓魋と虎嘯の顔が浩瀚の中で浮かんだ。 視線を外に投げながら、陽子はその場から動こうとはしない。 (なぜ、動かない…!) 「主上…お早く!!」 何をしているんだ と睨む浩瀚に、陽子は唇を噛んで声を上げる。 「でも…貴方は…!!」 「…!!」 その声に、浩瀚は動きを止める。 (主上…) 「‥私のことは御案じなさるな」 胸に何かが込み上げたが、彼はそれを押しとどめる。陽子が見ていた浩瀚に一瞬切ないような表情が過ぎって、でも彼はすぐにその上に、いつもの静かながらも自信に満ち溢れるものを塗り込めた。 「貴方は貴方のやるべきことをやって下さい。私は貴方だけに、力をお貸しすると決めています」 「‥!!」 浩瀚の口元がゆっくりと弧を描く。正気を取り戻し、光を湛えた瞳で、浩瀚はしっかりと陽子を見据える。 息が止まる陽子、そして反対に、彼女に向かって浩瀚は声を張り上げる。腕の力は限界にまで達していた。 「放せえぇ!斬られたいのか?!!」 「っ…!さあ…お早く!!」 陽子は唇を噛み締める。浩瀚の腕の力が、暴れる楓椿を持て余し、徐々に緩んできているのを、陽子は気がついていた。それでも、陽子は―小さく頷いた。彼の願いを受け止めて、彼女は窓際に足を掛けた。そのまま外に向かって、身を躍らす。陽子は風の中で彼女の思い出せない忠臣を振り返った。 「ありがとう…!」 ふっと浩瀚は不敵な笑みを湛える。一瞬で陽子はその場から落下していく中で、どこからか班渠の焦った声が響き渡った。 「台輔の御身が危険です」 「分かっている!」 城壁にかかる陽子の影から半渠が飛び出す。落ちていく身体の下に滑りこむ、班渠の毛皮の感触に触れた途端、一気に陽子は自分の身体が浮遊するのを感じた。目指すは緊迫する空気を醸し出す一つの外窓だ。それを目に入れた瞬間、何故かゾクリと陽子の肌が粟立つ。 「台輔」が誰かも分からない。ここがどこかも分からない。自分が誰かも分からない。 何もかも思い出せない中で、陽子はただ一つ…疼く胸奥を抱えて空を駆けた。 ::::: 広がる暗がり、窓際から淡く差し込む月の燐光。何も無い無音の世界で、景麒はだるく重たい瞼を押し開けた。 「う‥」 腹に走る鈍痛に、景麒は思わず顔を 目の前に佇んでいる―まがい物の王、漢轍に。 漢轍は薄ら笑いを浮かべながら、片眉を跳ねあげて見せた。残忍な笑みを深くして、漢轍は景麒を見やる。 「お前は‥思い出したんだな…?景麒」 真実を‥と言う低い声が響く。景麒がいつもより数倍は冷ややかな目で漢轍を見つめ、その視線が凍っているのに漢轍は気がついた。漢轍は首を傾け、眉を上げて景麒を見やる。小さく呟いた。 「麒麟でも…そのような目をするのか…」 景麒は何も答えない。漢轍はフンと鼻で嗤った。 「真実を思い出したのは面倒だが、好都合な部もある。どちらにしても、お前が思い出そうが思い出すまいが、お前は私の物だ。記憶が戻ったのなら、私の質問に答えてもらおうか」 「下郎が…逆賊の分際で、その様な口がきけるか」 「なんとでも言うが良い…。玉座が手に入るのなら、どんなことだってやってやる」 翳が、漢轍の顔に落ちる。角度が付いて、影の面積が広がったその顔は狂気に濡れていた。 「私が知りたいのは、王に相応しい『珠翼』の在り処だ。お前はそれをあの小娘から預かっている筈だ。」 「何だと…?!」 目星は既についている と言いながら、漢轍は探るように景麒を見つめる。思わず反射的に胸元に手を伸ばした瞬間、漢轍の瞳がギラリと脂ぎった光を湛えた。 「やはり隠していたか…」 思い切り景麒の手をつかんだ際、胸元から翡翠の首飾りが弾けるようにこぼれる。我武者羅に景麒はその手を振りほどいたが、衣から引きずり出され晒された首飾りは頼りなく揺れた。 その歪な削り面に幾重にも自分の姿を映しながら、漢轍は言葉を吐く。 「お前が玉などの飾り物を付けることなど皆無に等しいのに…早くそれに気が付くべきだった。それがあの小娘が引き渡した『珠翼』なんだろう…?それ以外に、お前がそれを肌身離さず身につけている理由が無い」 「…!」 景麒の瞳が見開く。 (何だと…?) 本当は、首飾りの意味など、景麒はまるで知らなかった。景麒がそれを側から離さないのはまるで違う理由からだったが、真実は分からない。 「そうなんだろう?他にお前がそれを持つ理由が有るのか?言ってみろ。それさえ手に入れられれば、お前だって私に喜んで跪く」 景麒は漢轍を視線を鋭くして睨みつけ、漢轍はしたり顔で景麒を見下ろす。 景麒がこの首飾りを肌見放さぬ本当の理由。それは本当はあまりにも単純で、大切な理由だった。自分と陽子だけが共有できる物だった。それは他者に踏み込まれたくない、景麒の心の絶対領域とでも言うのだろうか。 言えない と景麒ははっきりと自分の心が言うのを聞いた。 「認めろ。景麒。そしてそれを私によこせ」 景麒の頭に血が昇る。沸々と湧き上がる怒りの熱さに、声が震える。 「下らない‥。そのような考え方をすること事態が異常だ…。私はただ一人を除いては、誰にも頭を垂れることは出来ない…!私にとって、あの方以上の主などいない!!」 そうだ。全てを包む優しさ、自身の醜悪さと戦う強さ、纏う輝き、全てにおいて景麒にとって陽子以上の主はいなかった。何が起こっても他者のせいにしない強く優しい心を持つ、人が自然と頭を垂れる人物だった。怒りが沸点を突き抜けて、逆に景麒は自身の声が冷えたのが分かった。 「何も知らない分際で…何が分かる」 記憶にはためく真紅の髪。強い意思を湛えた翡翠の瞳。 主が美しいのは、見目が整っているからでも、絢爛な衣服を身に纏わされていたからでもなくて、その心が美しかったからなのだ。 男も女も、老いも若いも、敵も味方も、記憶が有ろうと無かろうと関係ない、誰もが惹かれるのは、陽子自身が育てた彼女の心の美しさだ。 震える景麒の唇から言葉はとめどなく流れ落ちる。漢轍が驚いて動きを止める中、声だけがその場に響く。 「何も理解しようとしないお前に…」 視線を研いだ景麒の目の前に佇む、自己の盲信に陥った漢轍。 「自分の本当の姿など見ようともしないお前に…」 記憶の中で苦闘する、常に問い続け、己の在り方を律しようと努力する陽子。 「人を隷属させることでしか、自己の正当性を見出すことの出来ないお前に…」 弱きを従えようとする漢轍と、弱きを守ろうとする陽子。二人の姿が景麒の脳裏に同時に浮かんで消えて、景麒は声を荒げて叫んだ。 「何が分かる!!!」 ピクリと漢轍の動きが止まった。言いたいことを吐き出して、肩を大きく上下させながら、景麒は俯いた。 剥き出しの自身の声になど気付くことも無く、景麒は普段表情に乏しい顔を歪める。あの光を弾く髪を見たかった。普段の慣れない墨に苦戦して手を汚す姿が見たかった。言葉の足りない自分を許してくれる、あの笑顔が―見たかった。 喉が焼けるような感覚がして、声が掠れる。 (主上…) その瞬間、誰にも聞こえない程の小ささで、掠れながらも熱くて想いの籠った声が、景麒の唇から――零れた。 「主上に…会いたい」 苦々しい顔を貼り付ける漢轍。うっとおしそうに首を振り、苛立ちを込めた顔で景麒を見下ろす。自分こそが玉座に相応しいと自負する彼にとっては権威を除いては何もかもが色褪せて見えた。目の前で揺れる翡翠の首飾り、それ以外の物に彼は微塵も興味が無かった。苛々と舌打ちをしながら景麒に向かって手を伸ばす。 「そんなこと知ったものか。どうでもよい!お前は私に従う獣だ!それ以上の価値など何もない!!さっさとその首飾りをよこせ!!」 「…!!」 太い指が迫ってくる。景麒の顔に影が落ち、彼は夢中で身体を捩ってその場から逃げようとする。金糸を乱暴に掴まれて、鋭い痛みと共に、何本かが抜け落ちた。景麒は苦悶の表情を浮かべる。そして漢轍は今にも翡翠に手を掛けようとしていた。 (主上…!!) 「よこせえぇ!!」 その時窓際に人影が落ち、月明かりが一瞬遮断されたことに…瞬間、景麒も漢轍も気が付かなかった。髪を引かれる痛みに薄目を開けた景麒の目の前に影が出来る。驚いて目を開く景麒。 ―――刹那。 窓硝子が、弾け飛んだ。 「?!!」 「んな?!」 硝子の砕け散る轟音、白く濁った幾多もの硝子の破片が、月明かりに染まって銀色に輝きその場を彩る。その光の粒の中に一人の少女が姿を現した。 銀色の破片の中で、目にも鮮やかな紅が―翻る。 「?!!!お前は…!!」 「!!!!」 翡翠の目の少女は目を細め視線をずらす。月明かりの逆光で、二人いる中でも、髭を伸ばした男の顔しか彼女には見えなかった。だけど、それでもどちらを打つべきなのか本能的に彼女は分かっていた。 部屋の中に踊り込んだ陽子は、剣の柄に手を駆ける。暗闇で目を見開く景麒と、思わず後退る漢轍の姿が目に映る。 深い闇の中、深緑の瞳が―輝いた。 |
| back index next |