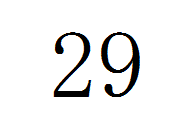 |
|
慶国の首都、堯天。普段は人の行きかう音で包まれているその街も、今は静かな夜の膜に覆われている。 闇に浸かった街並みを、駆ける二人の少女がいた。 風に跳ねながら、差し込む月影を弾く、漆黒の流れと紺青の深い波。静謐さが街並みに満ちる中、乾いた足音だけが木霊する。鈴は駆けながら、しきりに周囲に目を向ける。どこかで、あの常闇を弾く赤の波が見えないか、と微かな期待を抱いている自分がいることを否めなかった。 周囲には似たような顔をした家々が身を寄せ合って並んでいる。ここは市場のようだ。日が出て店を開けている時ならば、並ぶそれらの建物はそれぞれが違った個性の色を出して、場を彩るのだろうが、今は皆黙ったまま無表情を貼りつけている。その光景を見ながら、鈴は思わず唇を噛み締めた。 (あの人は…どこに居るのかしら…?) 王宮では、逆賊が堯天に紛れ込んでいるという噂で持ちきりだ。赤髪に、褐色の肌、緑の瞳の年頃の少女―それが「あの人」のことを指しているのか、鈴には未だはっきりとした確信が持てない。「あの人」が逆賊という汚名を被せられるような人物には、鈴にはとても思えなかったからだ。 柔らかい唇に食い込んでいく、自分の歯の感触が、鈍い痛みとなって鈴に感じられてきた。喉の奥が塩辛さで濡れる。 (あの人は、そんな人じゃないわ…!) そう心で声がし、鈴は強く瞑目する。だがその次の瞬間、実際に鈴の口から驚いた声が漏れた。 後ろから、祥瓊の掌が鈴の肩を掴んだのだ。 鈴は驚いて思わず振り返る。固い顔つきになった祥瓊は、瞬間的に振り向いた鈴の口を手で覆った。 (?!) 意図しない祥瓊の行動に、鈴の足が動きを止める。更に走っていた速度が重心を崩すのを手伝って二人はもつれて地面に雪崩込む。鈍い痛みに抗議の色を目に浮かべ、鈴は祥瓊を見上げた。対して祥瓊も必死の眼差しで鈴を (な、何なの?!祥瓊‥!) (しっ!良いから黙って…!) 鈴を抑えながら祥瓊は目線を、先程まで走っていた方向に持ちあげて見せた。それに釣られるようにして鈴も黒眸を上げる。同時に、丸く開いた鈴の唇から漏れかけた声を、上から白い手が再び塞いだ。 鈴の口の中で、声は形にならずに崩れる。 (桓魋…!虎嘯‥!) 一瞬、旧友である彼らの元に駆け寄ろうとした鈴を祥瓊が抑えこむ。驚いて振り返った時に見えた、祥瓊の顔に浮かぶ僅かな恐怖、彼女の表情の意味が分からず、鈴は動きを止めて彼らを見つめ直す。 戸惑ったように、鈴の睫毛がゆるりと上下する。 鈴の瞳に映る、二人の男。 何度か瞬きした時に、鈴は彼らの異常さにゆるやかに気が付き始めた。普段なら共に居て、心地良いと感じる二人の目に見える体温からは、今は温みを感じ取ることさえ出来なかった。氷点下を思わせる低い温度の瞳が、そうさせているのか。彼らの肩の線が揺れるだけで、湧き上がるこの恐怖はなんなのだろう。布を越して伝わる祥瓊の細かな震えから、鈴は彼女も同じ恐怖を味わって竦んでいることを知った。 垂れ流されるのは慶国最強の戦士が放つ、無差別の覇気だった。触れたら、皮膚が裂けるような戦う男の覇気。二人の中でも普段温和な桓魋を瞳に映した瞬間、鈴は絶句して自分の口が開くのを感じた。 (今は…動いちゃ駄目よ、鈴‥) 囁かれる祥瓊の声は酸味を帯びて緊張している。遠目からでも確認できる二つの輪郭を視野にいれながら―鈴はただ一度だけ、頷いてみせた。 それからどれだけ時間が経っただろうか。二つの男の影が消えた後も、重なったまま小さくなっていた二人の娘は、のろのろと身体を起こす。二人の様子を思い出して、身体の芯から震えが湧き上がった鈴は寒気を消すように掌で何度も腕を摩った。 「あの二人…どうしたの…?特に‥」 桓魋 と呟き零れた声は、自分の声とは思えない程凍えていた。祥瓊は薄紅の唇を、音が出る程強く噛み締める。 「全部‥今在るあの男王のせいよ…あの二人は、特に…桓魋は、今正気を失っているわ」 そんなと鈴は目を見開く。暗闇に染まり、薄墨の砂吹く地面を睨みつけていた祥瓊は、引いていた顎をゆっくりと持ち上げる。 「だから、私達は今の彼らの至近距離に近づけない…。あの人達のためにも、私達が犠牲になったら話にならないわ」 「じゃあ…どうするの?」 祥瓊は闇にならされた空間を睨む。沈黙の間に差し込む月明かりは青く透明に降り注ぎ、虎嘯達が消えていった、白い砂を塗した道を反射して光らせている。その絹のように伸びる光の道を見つめたまま、祥瓊は結んでいた唇を割った。 「…虎嘯達を追うわ。但し、見つからないように。どちらか一人でも見つかったら、お互い自分のことだけを優先して逃げるのよ。絶対に、捕まらないようにね」 鈴は祥瓊を見上げる。祥瓊の瞳は揺らぐこと無く、虎嘯達が消えていった一点だけを見つめていた。 「命令されたあの人達が向かう所にはきっと何かあるわ…それが私達の記憶の鍵になる可能性があるんじゃないか、って私は今思うの。もうこれ以上あの男王の思い通りになんてさせないわ。させるもんですか」 祥瓊の言葉を聞きながら、鈴の顔つきは鋭く締まっていく。無くした記憶も、 桓魋達も、何もかも取り戻してみせる―そう決意を固めた少女の瞳は、揺るがない光輝を纏っていた。 ::::: 静かな筈の街並みのある一点、二人手を取り合って泣き笑いを浮かべる陽子と楽俊。埋もれて見えなかった絆を見つけ、強くした彼らの元に―「脅威」は音も無く…忍び寄る。 二人で佇むその夜の最中、最初に異変に気がついたのは、陽子、だった。 「?!」 唐突に、背筋の凍るような悪寒が陽子を撫でた。 「よ、陽子?」 驚いて飛び上がった陽子に、楽俊が僅かに心配そうな顔をする。はっと彼の声に気がついた陽子は慌てて掌を振って見せた。 「い、いや…何でも無い…」 そう言いながら、陽子の目つきが鋭さを孕んで、周囲を警戒し始めたのに楽俊は気がついた。彼女の周囲の空気が変わる。楽俊は何が何だか分からないまま無言の緊張が走り始めた周りを見渡した。陽子の翡翠が、広がる夜の闇を掬い上げる。 (何だ…?このとんでもない…) 殺気は。 強く風が吹き、陽子の括った髪を靡かせていく。風に含まれた殺気の、ぬるりとした禍々しさが陽子を撫でていく。粘り気の在る闇の中、陽子の睫毛がゆるりと目を覆い、また持ち上がる。 陽子がますます視線の鋭さを研いだ時、背後で開け放たれた扉から、夕暉が弾くように飛び出してきた。 「お姉さん!!良かったまだ居たんだね、今遠くで何か轟音が…」 弾む声は安堵と焦りが織り交ざる。言いかけて、夕輝は陽子の戦闘態勢の気迫を察し、口を噤んだ。 体積を増し、存在を主張し始めた殺気を、彼もその瞬間感じた。 佇む三人を包む、煮え切らない闇。 空白がどす黒さを帯び始めた次の瞬間、背後で物音が響くのと陽子が白銀を鞘から抜き放つ金属音は同時だった。 「誰だ?!」 即座に楽俊を後ろ手に庇いながら、鋭い声が殺気で濁った空気に響き渡る。粘り気を無くし、さらさらと身体をすり抜け流れ始めた深い闇。闇に溶けた濃い殺気。 ますます濃度を上げながら、それは大きさを増していく。ふっと側方で走った気配に陽子は白銀を閃かせ、敵の襲来に構えを取ろうと身体を捻る。 だが陽子と夕輝が構えを取り切る前に― 襲撃が三人に牙を向いた。 一瞬遅れて夕輝が前方に弓を引き絞った時には、巨大な落下物が三人の頭上に濃い影を落としていることに、陽子は瞬間的に気がついた。 振り仰いだ瞳に映るのは、投げられたままの角度で上空で動きを止める、巨大な石塊だった。 心の中で幾つもの声が錯綜する。 いつの間に、こんな…! どんな力で…?! いや、それ以上に速さだ‥! 何故?ありえない、何の気配もしなかったじゃないか!! とにかくこの二人だけは‥巻き込めない! この二人だけは… この二人だけは!!! 一瞬にして陽子の脳裏に弾かれる思考の数々。だが、どれも言葉になんてならなくて、陽子はただ目を見開く。 「なっ‥!!」 声にならない言葉と共に陽子は咄嗟に夕輝を影の外に突き飛ばす。そして楽俊を抱え、遮二無二、落下物が落とす影から転がり出た。考える以前の出来事だった。 「うわっ?!」 「っ…!!」 弾かれるようにして楽俊と二人で地面に叩きつけられた次の瞬間、石畳が砕ける轟音が響き渡った。陽子、楽俊、夕輝が見たものは、先程自分達がいた場所に、巨大な、陽子の身丈程もある折れた石柱の数々が砕けてめり込んでいる光景だ。まるで誰かが力任せにねじ切ったような石柱の断面に、楽俊が悲鳴を上げる。 「な?!なんだこりゃあ…!」 楽俊の狼狽する声が、妙に遅く感じられる。速度を増して彼女を攫って行こうとする殺気の流れに足を踏みしめ、陽子は水禺刀を構え、僅かに走った気配に向かって駈け出した。碧双珠を夕暉に投げ渡し、陽子は視線をぶれさせずに、狙いを定めた一点だけを見つめたまま突き抜ける。 夕暉は突然の事に混乱しながらも、空中でそのとろりと碧い珠を捕まえた。 「?!お姉さん、これは…?!」 傷を負ったらそれを使え と旅の中で気づいたその珠の効力を陽子は後ろ背に叫ぶ。この二人だけは、失いたくない。 「楽俊を頼む!!!」 「お姉さん!!」 白銀が空を切り裂き振り下ろされる。何も見えなかった夕暉が次の瞬間聞いたのは、凶器がぶつかり合って牙を剥く甲高い轟音だった。弾かれる高温の閃光が闇夜に一瞬だけ輝いて、消えて、その闇をより深く彩る。濁った砂煙が吹き荒れた。 膨らむ砂煙から飛びすさぶ二つの影、一つは紅の波を振り乱す少女。もう一つが分からず、夕暉は目を細める。 (何者なんだ…?!) ただ一つ分かることは…自分が知っている、誰よりも、強い。それは恐らく兄の虎嘯よりも。一瞬で投げられた、石柱の数々が、その影の尋常では無い戦闘能力の高さを物語っていた。一つ一つの手でねじ切られたようなひねりのある断面に、夕暉の背筋を寒気が走った。相手はよほど、常人離れした力がある。 体勢を戻した陽子は、荒くなった息を肩で整えながら、渦巻く砂煙を睨みつける。 (妖魔か…?!) 少なくとも、唯の兵士では無い。だが、妖魔にこんな的確に標的に向かって凶器を投げることなど出来るのか。疑念が渦を描く陽子の心情は唸りとなって、漏れる。疑問に答えるように、綿雲に覆われていた月が、身を捩り、光をそっと零し始めた。 濁っていた砂煙に、上空から光の帯が落とされていく。その瞬間、光と溶け合った所から白く澄んで、その影の輪郭を陽子達の目の前に透かし出す。瞬間、月光を攫うよう吹いた強い風が手伝って、白の砂煙を剥がしていった。 砂粒が弧を描きながら、影から剥がれて闖入者の輪郭を映し出す。月影が、光を落として影に着彩をしていくと同時に、影を睨みつけていた陽子の瞳が、ゆっくりと見開いていく。 固い、身体の線が目に入った。その線は、鈍く光を纏って、揺れる。影は予想していた妖魔なんかじゃなく… それは――自分の身の丈よりも巨大な長槍を持つ、固い甲冑に身を包んだ一人の男だった。 陽子は呆然と瞬きする。襲撃者は自分が何者かすら覚えていなかった。自分が禁軍の将軍であることも。自分の名さえも。理性と心を失くした瞳はただ一人を見つめる。 桓魋の零れた前髪が、風に吹き荒れ、乱れた線を形創る。彼の顔を光が照らすが、相反するように、その相貌には深い翳りが巣食っていた。そして何よりも‥見る者の肌を粟立たせるのは、その瞳の奥に溜まるどろりと煮立つ炎の揺らぎだ。 彼の背丈よりもゆうに大きな巨大な長槍。その刃の鈍い滑らかさが月影を吸い込み、嗤う。夕暉が後ろで息を呑む音が響いて、武人の相貌を瞳に映した瞬間、陽子は思わず口を開ける。 身も凍る殺気の源を、陽子はその時―肉眼で捕らえた。 |
| back index next |