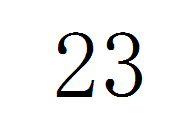 |
|
「どういうことだ!!何故あの女を仕留めずに帰ってきた!!どうかしているぞ!!お前を見込んで送り込んだ物を、一体何をしている!!!」 怒号が、薄闇が包み始めた金波宮に響き渡る。蝋燭の明かりだけが濃さを増していく債務室の中では、漢轍の顔は怒りで夜目にも赤く染まっていた。それを気怠げな仕草で聞き流す髪を結い上げた女―いや、男は薄目を開けて漢轍を見下ろす。漢轍もかなり上背がある方だが、この男のほうが更に背が高かった。 遠征から戻るなり漢轍に呼びつけられた楓椿は、首筋を掻きながら、緩慢な吐息をつく。ふ と音を立てたその口角がゆるりと持ち上がった。 「どうかしているのは貴方の方だ。あれ程お美しいお方を葬るなどよく考えついた物だ。何と言おうが、あのお方は私が手に入れる。口出しはしないで頂きたいな」 光にたなびく真紅の髪。張りのある瑞々しい褐色の肌。吸い込まれるような、深緑の瞳。太陽の色合いと、人を潤すような水源の色合いを持つ少女の美しさは一目見た時から瞳の奥に焼き付いていた。しかし…と楓椿はうっとりと呟いた。 「何よりもお美しいのは凛としたあの立ち姿勢とあのお方の生き様なのかもしれない…」 恍惚の表情を浮かべて楓椿は拳を握り締める。 そんな楓椿の様子を見て、漢轍は忌々しげに舌打ちした。 「ふざけおって…!宝重も奪われた!どうしてくれるんだ!!」 「おや、そう仰るがそれは元々はあのお方の物だったのでは?」 「黙れ!!お前は一体どちらの味方なんだ!!」 激昂する漢轍に、楓椿は気怠げに片眉を上げて見せる。 「答えるのに億劫な質問をなさるな。貴方は何か勘違いをされているようだが、私からしたら元々は暇つぶしがてら乗った話、そのことを理解なさっているか?私は元来王座になど欠片も興味がない。ただの利害の一致から私達は共に居るだけ。だから戦士として、周囲の目に留まらぬよう男であることを隠せという貴方の命令にも従った。まぁ結果的に女のふりも悪くはなかった上、想像以上の素晴らしいものに出会えたことは感謝いたしたい所だが」 フンと楓椿は鼻で笑い、双眸を薄く光らせ笑みを浮かべる。その強い口元の傾斜は見るものがいたら怖気を与える物だった。 ふ と彼が息をついた次の瞬間、部屋に滑らかな金属音が響き渡った。 楓椿は漢轍が反応する間も無く、腰の鞘から刀身を抜き放ち、漢轍にその刃を向けていた。蝋燭の温もりを冷えた白銀が映しだし、その刃に弾かれた、歪んだ暖光色と、不可思議に伸びた自分の顔を漢轍は間近で見合った。 「!お前…!」 刃を揺らす楓椿のその目は爛々とした明かりで濡れていた。苦い顔を貼り付けた漢轍とは反対に、笑みを浮かべた楓椿の相貌からは何一つとして読み取ることは出来なかった。ただ、淡々と彼は目の前の男に突き付ける様に、囁く。 「私は国にも民にも興味は無い。ただあのお方だけは私が貰いたい、それだけだ。貴方は王座を取れば良い…喩えそれが偽りの頂点だとしても私は止めはしない。玉座などくれてやる。だが私達の関係性は、今私が突き出した条件を許せぬのならここで決裂だ…」 「お前…」 「是か否か、今この場で答えて頂きたいな」 もし是なら…と楓椿は瞳を逸らさずに続ける。目を閉じた彼の脳裏に浮かぶのは美しい翡翠の瞳の少女の姿だ。合間見えた時に剣花を散らして伝わってきた少女の強さにゾクリと背中が粟立つのを感じる。 漢轍が睨む中、彼の口端が更に持ち上がった。 低い声がゆっくりと形を持って―響いた。 「私の力を御貸ししよう」 ::::: 夜の回廊は、全ての音を吸い取ったように酷く静かだ。そんな静謐な回廊を、柔らかい衣擦れの音を響かせながら一人の人影が横切る。括り上げられた夜の輝きを纏った漆黒の黒髪が揺れ、青めいた艶を走らせていた。堂々たる偉丈夫と呼べるこの男は、ただ前を見つめて歩みを進める。精悍な顔つきの男からは今は表情が消え、その相貌から彼の心情を伺うことは出来なかった。 角を曲がり、月明かりが顔を覗かせる外廊に、男は足を進める。その時、青白いその光の中で、佇む一人の少女の身体の線を男は目に捕らえた。少女は足音に気がついてこちらを振り向き、慌ててその場に口頭する。それは優しげな印象の少女だった。 「え、延王陛下…!」 良い と男―延王尚隆は少女に顔を上げさせる。延に少女は一度礼をして顔を合わせた。 「この度の王君のご訪問、慶国官仕共は誠に喜悦しております」 尚隆は薄く笑った。 「固くならないでよい。丁寧な挨拶は礼儀だろうが、俺は堅苦しいのはあまり好きではなくてな」 「か…堅苦しい…ですか」 顔を真赤にして今にも緊張でひっくり返ってしまいそうな少女に尚隆は大きく笑った。そして、先程の少女の横顔を見て気になった言葉を彼女に投げかける。 「こんな所で何をしている?」 「いえ…ただ、ちょっと考え事を…」 「ほう?」 少女は本当に、滅多に話すことも無い王君の手前、恥ずかしそうに俯いて、言葉を必死に探す。延は彼女が話し始めるまで、待っていてくれた。尚隆が通りかかるちょうどその時、その少女は一人胸のうちに巣食う不安と対峙するように、濡れた月明かりを一人見つめていたのだ。尚隆にとって名も知らない少女はずっと迷ったように顔を揺らしていたが、やがて思い切ったように声を出す。 「最近の自分と周りのおかしな事についてずっと考えていたんです」 「おかしな事?」 はい と言った少女は真摯に延王尚隆の顔を見つめる。その声は初めて誰かに打ち明ける様な、僅かに拭えきれない不安が滲んでいた。 「私は、何かをずっと忘れている気がしてならないんです。とても…とても大切だったものを‥。そして私の周りも同じように何かを忘れているように見えるんです。私の友人も、両親も、全ての人が何かがおかしいのです。誰かに何かを変えられてしまったような…。おかしいと思われるかもしれませんが、私には今の慶国に何か異変が起こっているとしか考えられないんです」 ピクリと尚隆の動きが止まった。変ですよね と組んだ指を見つめながら、少女は言う。少女は王宮に召し上げられてから今まで何の問題も無く暮らしてきていたが、ある時から何かがおかしい気がしてならなかった。そして最近になって決定的に気がついてしまったその違和感。彼女の友人達、そして田舎で暮らす両親までそれは当てはまった。少女から見たその異質な雰囲気は何もかもから感じ取られて、拭い去ることは出来なかったのだ。 肩を震わせる少女は恐る恐る延王を見つめ上げる。だが、延は優しく笑って、励ますように少女の背中を叩いた。 「大丈夫だ、何も変わってなどいない」 え?と顔を上げた少女の肩に尚隆は手を乗せる。その手は温かく、肩に溶ける温度に思わず少女はどきりと胸を高鳴らせる。 「俺が見たこの国は皆元気な良い国だったぞ。大丈夫、きっと気のせいだ。勿論今目の前にいるのも含めて、女は皆良い女だしなぁ」 「え、延王君…!」 「おっと、今のは本気だからな。これだけ綺麗な女がいる国は良い国だ。安心しろ」 ひたすら照れる少女に笑いながら、尚隆はポンポンと彼女の肩を叩いた。少女の顔はまだほんのりと赤かったが、彼女は少しだけ、安心したような表情を見せた。少女の様子を見た尚隆は微笑む。暖かそうな少女の頬とは反対に月の光の筋が流れる外廊は青みを帯びて、そして尚且つ少し肌寒い。その向こう側の闇に消される己の進む道に尚隆は少しだけ目を細める。その黒眸を通して、一体彼は何を思っているのか、読み取ることは難しい。 薄暗い床に足を踏み出した尚隆の背に、少女の声が投げかけられた。 「あ、あの…!」 「?何だ?」 振り向いた尚隆に少女はペコリと頭を下げる。 「あ、ありがとうございました。わ、私今までずっと怖かったのですが、今のお言葉で元気が出ました」 尚隆はニッと笑った。 「それは良かった。また元気が欲しいのならば俺の所に来ても良いんだぞ」 「お、王君!」 冗談だ と豪快に笑いながら延はその場から去っていった。少女はその後姿に深々と頭を下げて、ほっと胸元の不安を気のせいだと抑えこむ。少女が見つめる精悍な男の後ろ姿は闇に飲まれて消えていった。 だがその時、少女は気が付かなかった。 後ろ手に手を振る延王から、頭を痺れさせるような甘い香りがしたことに― 正面からみた彼の瞳が何かと戦う様に揺れていることに― その足が僅かに震え、顔から脂汗が滲んでいることに― 少女は最後まで気が付くことは無かった。 ::::: 等間隔に並ぶ蝋燭の明かりだけが夜の闇に滲む。尚隆は僅かに震える手で、慶国の王の執務室の扉に手をかけた。半ばぶつかる様にして扉を開け、彼は中に崩れ込む。 そこで余裕綽々の笑みを浮かべる男を、尚隆は轢かれた絨毯の上から睨み上げるようにして目に入れた。好き放題に四方に伸びた髭が動き、尚隆は男が笑ったのを感じた。男は尚隆の元まで歩き、彼の目の前で足を止め、上空から彼に声を落とす。 「これはこれは延王君…。ご到着が遅いので何かあったのではないかと、使いを出そうかと思っていた所」 尚隆は息を荒げながら目の前の立つ男を睨みつける。彼は男を見ながら吐き捨てる。 「礼儀とも言えぬ礼儀などいらん。お前が‥お前がこの事件の黒幕だったんだな…」 「漢轍と申す。今は景王と呼んで頂きたいな」 「景王…?お前が?」 せせら笑うように言葉を零す尚隆は、重たい身体を引きずるようにして顔を上げる。その瞳だけを燃やして、尚隆は漢轍を睨み上げる。 「景麒の選定も受けぬお前が景王だと‥?戯言も休み休み言え」 漢轍は尚隆を見下ろしたまま薄く笑う。 「そのような口を叩けるのも今だけだと。やはりさすがは延王君と言うべきか…治世五百年の王は違うようだ。これだけの香に塗れても、まだ理性と正気を保っていられるとは…。実に屈強なお方だ。延麒に手が届かなかったのが口惜しい」 尚隆はピクリとも顔を動かさずに囁く。 「異変を感じ、報告を受けた時から家の麒麟には慶の出入りを禁じてある。余程の重大事件が起きるか、景王失踪というこの不可解な事件の目処が着くまではあいつを危険に晒すつもりは無い。俺は自分のものを簡単にやる程…心も広くないのでな」 「左様だったか。いやはや麒麟は延王の手の回りの方が早かったということか。だが肝心な貴方は今ここで得意な剣技も披露出来無い有様だが、それも計画の内なのかな?」 尚隆が自分を睨みながら唇を噛むのを見て、漢轍はほくそ笑む。 「ご安心為さるがよい。私は慶の者。雁をどうこうしようなどとは思うておらん。ただ…私の存在を容認する他国の王が私は欲しかったのだから。実際、私が真に狙っていたのは貴方一人。本当なら麒麟も手に入れば言うこと無いが、貴方を手中に入れた今、まぁこれで目的も達した…」 尚隆は低く唸る。 「俺が‥お前のような偽王を認めるとでも?」 漢轍は笑みを口元に貼り付ける。 「直にそうなる…。今貴方が正気を保っているのは予想外だが好都合。何かと嗅ぎ回ってくれたようだが正気を保っている内に聞きたい事がある」 漢轍が横目で尚隆の様子を見ながら小馬鹿にしたように笑った。尚隆はその発言に反応を見せずに押し黙る。唐突に、彼を纏う空気が甘さを濃くした。 (まず‥いな…) 尚隆は急激に意識が何かに揉まれるような感覚を感じながら、必死にそれに抗う。 意識が朦朧とする尚隆を目端に入れながら、漢轍の瞳が大きく見開いた。尚隆の様子など一向に構わず漢轍は言葉を続ける。その目にゆらりと乾いた炎が揺れた。 「『十二帝の珠翼』正式名称を『鵬珠翼』…十二の国にそれぞれあると言われる宝玉はどこにある?珠翼は雁国にも有る筈だ…。貴方はそれを持っている、それをどこで手に入れたのか洗いざらい話して頂きたい…」 尚隆の黒眸が僅かに見開いた。 「鵬珠翼‥?何故お前がそんな物を…」 漢轍は血走った目で尚隆を見ながら、彼の胸ぐらを掴む。息を荒くしながら、漢轍は口だけを動かした。 「それこそが私がずっと探し求めている物。慶にもそれはある筈なのだ。王としての素質を称えるその宝玉。世界にあるどんな物よりも美しい宝玉。それさえ有れば麒麟も自ら膝を折り、私を王と認める筈。その宝玉を私は何としてでも手に入れて、女王を排し、男王こそが素晴らしいことを世界に照明する。お喜びなされ、その栄光の革命の一員に私は貴方も入れてやろうとしているのだから」 目だけを血走らせ、剥き出しの狂気に塗れたその顔は見る者を震え上がらせる。空気が震え、蝋燭の明かりが靡いて消えた。煙だけが細く部屋にたなびいていく。一際濃い花の臭いに、尚隆は目の前の色が揺らぐのを見た。 だが、彼は意識を朦朧とさせながらも、微塵も漢轍に怯む様子を見せなかった。漢轍が尚隆を凝視して答えを待つ中で、尚隆は意識が揺らぐのを感じながらも、口端を釣り上げる。一瞬の沈黙の後、尚隆は一言はっきりと呟いた。 「お前には無理だ」 「?!…何だと?」 尚隆は口端を益々上げて、歪む景色の中淡々と続ける。 「そんな物を信じている莫迦がいたとはな…。確かにその話は俺も聞いたことがある。伊達に五百年生きていた訳でも無いからな…。奏の風来坊がかつて聞かせてくれた…。だがそれはお前が言ったような話では無かったがな…?」 「?!‥どういう意味だ」 「話しても無駄だ。お前は恐らく受け入れん。一つだけお前が求めている答えになり得るとしたら…それは皆が言うような形ある宝石、などと言う物では無いというくらいか・・まあいずれにしても、お前には到底手に入れられないだろうな…そもそも、そんな物は迷信だと俺は考えている」 それ以前に…と尚隆は言葉を切る。すっとその視線を漢轍に合わせた。舌足らずになりそうな言葉を紡ぎ、尚隆は真実を突き付ける。 「王は…麒麟が選ぶ。そのことさえ受け入れられない阿呆に玉座だと‥?馬鹿馬鹿しい。紛れも無く、選定は既に終わっている。お前が真に王…なら‥ば、ずっと前に景麒の方からお前の元に…出向いているだろう。‥ 「!!‥黙れ!」 「王宮の人間も、‥少しずつ、異変に気づく者が現れ‥ている。何をしようと…無駄‥だ」 尚隆は薄く目を細める。意識が暗くなっていくのを感じながら、彼は呻いた。吐息を霞ませながら、尚隆は眉根を寄せる。本格的に、震える意識が限界を告げ始めていた。 「黙れと言っているだろうが」 漢轍が怒りに顔を染める中で尚隆はその言葉を無視した。それに…と呟きその口元に、彼らしい にひるな笑みを湛えた。 「お前じゃ…あいつには敵わん」 漢轍の目が見開く。激昂した漢轍は尚隆の胸ぐらを突き飛ばした。 「黙れ、黙れ黙れ黙れ!!」 燻った瞳は爛々と狂気だけを燃やしていた。扉に叩きつけられて、背中から流れこむ衝撃に腹の奥から咳を零す。延王尚隆は、もうその時には僅かに残る意識を揉まれながら、ぐったりと扉に身体を預けていた。僅かに滲んだ汗が彼の頬を滑っていく。漢轍は、肩を上下させながら囁いた。 「王座にふさわしいのは私なのだ。誰が、なんと言おうと…!お前も使ってやる…。珠翼は必ず有る筈だ!あの忌々しい小娘がきっとどこかに隠したんだ!!」 漢轍は息を荒げて、意識の崩れる縁を彷徨う尚隆を睨みつける。目を見開いたまま誰に言うでも無く、漢轍は囁いた。 「そうだ…きっとそうだ。お前も私を惑わせるためにこのような戯言を抜かしたのだ。そうなのだろう?あの小娘は私が手を回す前に、珠翼をどこかに隠したんだ」 一瞬焦りが滲んでいた漢轍の顔は再び狂気に塗れていく。尚隆は何も答えない。自身の言葉に落ち着きを取り戻し、満足気な笑みを浮かべた漢轍はゆるりと立ち上がって小さく嗤う。 ふと、何日か前に運び込まれた慶国の麒麟を思い出した。景麒は仁重殿に運び込まれてから、意識を未だ取り戻していない。ずっとずっと彼が大切そうに握りしめていたあの首飾りが漢轍の頭を過る。何故、景麒はあの歪な首飾りをあれ程大切にしていたのだろう と疑問が湧き出、やがてはたと何かを思いついたように漢轍は目を見開く。 (…もしかしたら…あれが…) 漢轍は薄く尚隆を見やる。 「フン…いくらお前が虚偽を申し立てようと、私は必ず珠翼を見つけ出す。必ず、だ。あの小娘の生きる道も残してはおかん。楓椿との交渉内容とは違うが、最後にはあ奴も消し去る…。利用するだけ利用してやる」 部屋に漂う甘やかな香りはたっぷりと空気に溶けて、その場を満たしていく。漢轍は少しだけ扉を開け、その時通りかかった女御の一人を呼び止めた。 「延王が酒に酔ってしまわれた。人出を集め、寝所にお運びしろ」 女御は慌てて頭を下げ、そして大急ぎで人を呼びに駈けて行った。 漢轍はその様子を見送った後、くつくつと昏倒する尚隆を見て不気味に嗤う。 「お前も、駒の一つだ…。お前がこの国の王と認めていた人間をその手で消して貰う‥。十二国最強の剣豪の力を楽しみにしているよ。その時には、新しい景王を認めて、隣国同士仲良くやっていこうじゃないか」 答えは返ってこない。囁かれる言葉に呼応する様に、意識を無くしてからも強く瞑目し、きつく結ばれていた延王の眉根は徐々に、徐々にほどけていった。 漢轍は 次に目覚める時が楽しみだ と小さく呟く。そして目を細め… ―手前で揺れる蝋燭を吹き消した。 |
| back index next |