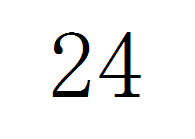 |
|
薄闇は、濃さを増して、溶けてゆく。 指令により金波宮まで連れられた景麒は、運び込まれた仁重殿の牀榻の上、その身を横たえていた。紗を掛けた天蓋を透かして見る彼の横顔は、弱く輪郭が暈けて薄い衣と溶け合っているようにも見える。 大理石から彫り上げたような繊細で美しい顔立ちは今はただただ白く、その眉根は苦しげに中央に寄せられていた。意識の浮かばない彼の顔立ちの奥で滲む苦悩、真実は閉じ込められたまま、静かに景麒の覚醒を待っている。そして景麒は、深い深い (‥ここはどこだ‥) 幻想の中、焼き付く己の主の姿だけが瞼の奥に濃い陰翳を落とす。そして想いは波のように上下を繰り返しながら、景麒の脳裏に押し寄せては溢れ、波打つ記憶の波頭は揺らめきながら千切れていった。 ―早く、早く目覚めなければならない 心に浮かぶのは焦燥か。その心の隙間に流れこんだのは、喧嘩をしたあの日の傷ついたような主の顔。あれは…あれは明らかに―大切な部分を刺された人間の顔だった。 悲しげに歪んだ眉、見開いた瞳、僅かに開いた震える唇の線が―心に焼き付いて‥離れない。 『お前にとって私が主であることは不満なのか?』 (違うのです…主上…) 違う。あんな顔をさせたくて、自分は主の元に行ったのでは無かった。 『麒麟は主を選べぬ生き物ですから』 言いたいことはそんなことでは無かったのだ。 喉が塩辛さで濡れ、景麒は呼吸が詰まるのを感じた。国、民、政、全てを背負う彼女には、景麒が彼女の世界の全てになることなど到底有り得ないことだった。けれど景麒にとっては何よりも、何よりも一番大切なのは彼女でしか有り得ないこともまた事実だった。彼女は王で、彼は麒麟。王は国のために存在し、麒麟は王のために存在する。 彼にとっては―彼女こそが彼の世界の全てだった。彼は彼女のためだけに、存在していた。 記憶の渦に抱かれながら、景麒は精神だけで、無いはずの瞼を強く合わせる。 過去の自分は、穏やかな日々を望んでいたつもりだった。 仁と平安に満ちた、国が有り民が有り王が有る様な理想をどこかで夢見てた。 (けれど…!) 息苦しさに襲われながら、あの主と共に歩むのに「平安」なんて言葉は無いに等しいのでは無いかと、景麒は今心からそう思った。 無理なのだ。 正当な王は悪意と対極に有る人間、悪意を摘み取り仁道を貫く人間だ。王は常に人々の内に巣食う悪意と戦い続ける立場であり、そしてそれは時として、自分自身さえもが敵と為り得る立場なのだ。慶国の平安は景麒の主の努力によって生み出される物なのだ。陽子が、彼女が醜悪と戦い続けることによって。慶がどれ程平和になっても彼女と共に居る限り、平安なんて有り得ないのだ。 景麒に出来ることなんて限られている中、陽子は、彼女は何としてでも景麒を危険から遠ざけようとするだろう。だが、彼女と離れる事で平安が訪れるのならば― それならば‥そんな物など要らない。本当に欲しいものは 彼女の傍居て、痛みを分けてもらえる存在でありたい。どれほど辛く、苦しい道のりでも共に歩めるのならば―何も要らない。 大切なあの人を、自分は支えていくことが出来るだろうか。 景麒の脳裏に、今まで記憶を無くしていた自分たちが、彼女を守り支えるべきだった自分たちが陽子に何をしてきたか、残酷なほど美しく、克明に浮かび上がる。妖魔に襲われる自身の主の姿を思い出した途端、景麒は胸を引き毟られるような痛みに叫んだ。そして痛みの中で、何よりも、と景麒は呻く。 自分は一番大切な所で決定的に何かを間違えてしまった。 その瞬間を思い出すだけで景麒は自身に吐唾したい衝動に駆られる。何が仁の神獣、麒麟。ただ一人のかけがえの無い人物を深く抉っておいて、何が、慈愛の生き物。 (申し訳ありません…) 苦いものを堪えるように景麒は「あの日」を思い出す。喧嘩をしたその日の主は、いつもなら付ける使令も付けさせず、誰一人として言付けさえ残さなかった。 言葉を間違えるべきでは無かった時だったのだ。 そのせいで自分たちは罠に嵌り、彼女を深く深く傷つけた。ただ素直に、本心を言えば良かったのだ。本当は無関心を装っていた景麒は、あの日一人―いつもよりも格段に帰りの遅い主人を待っていたのだから。ずっとずっと…待っていたのだから。 ――どうしてあの時、ただ、胸が潰れる程、心配していたと‥自分は言えなかったのだろう 脳裏から消えていく主の顔、広がる星屑を 景麒は紫眸を見開いて、今いる、ただ美しいだけの世界から藻掻くように腕を伸ばす。 言わなければならないことがある、それを直接、自分は伝えなければならない。濃くて澄明度の高い世界の一点に小さな光の綻びを、その時景麒は見つけた気がした。意識だけの彼は足場を掴んでいない足に力を込める。 そしてその綻びに向かって――高く跳躍した。 水面を目指すように意識は精神の深海から浮上する。 光を吸って揺らめく意識の水面から、顔を出した瞬間、景麒は牀榻の上に叩きつけられたような衝撃と共に目を見開いた。 「主上!!!」 飛び上がるように身を起こし、景麒は鼓動の激しい胸元に手を当てる。熱を帯びた掌に、何か冷たい物が当たって、それが彼を落ち着けた。景麒が視線だけを下に滑らせて見れば、胸元で身を休めていたのは肌身離さず持ち歩いていた歪な翡翠の首飾りだった。景麒はそれを握りこむ。 何故今まで自分がこれを手放さなかったのか、蘇る記憶から、景麒が痛いほどに理解した瞬間だった。 彼女がどんな意味合いを込めてそれを渡したのか、それは景麒には分からない。だが、それは今は景麒と引き離された主が唯一残した物。まるで主の深く澄んだ瞳と同じ輝きを持つそれを、景麒は身体を丸めて握った。 女怪が淡く落ちた影から滑り出し、気遣わしげに景麒の背を撫でた。景麒はその腕にゆっくりと視線を這わせる。そして芥瑚に目線を合わせぬまま、彼は小さく唇を割った。 「お前は‥思い出したのか‥?」 「?思い出す‥とは‥?」 少しだけ、眉根を寄せる自身の女怪に、景麒は透ける金の長い睫毛を上下させる。そして‥「彼女」のことを思い出したのが自分だけである事実を、下僕の戸惑う様子から悟った。景麒は視線を持ち上げ、真摯に芥瑚の顔を見つめて口を開く。 「‥一番忘れてはならぬことだ」 「台輔‥」 景麒は牀榻の上で柔らかな 「――――…」 言葉を聞きながら、僅かに驚いたように班渠の瞳が見開いていった。 「ですが台輔…」 班渠は言葉を続けようとしたが、景麒は視線を動かさずに切り捨てた。 「命令だ」 行かなければ‥と囁いた景麒は牀榻に手を掛け立ち上がろうとする。 だが、女怪が白い手を差し伸べたと同時に、その時大きく 「‥?」 立ち上がりかけた景麒の眉根が寄る。扉は不規則に震え、景麒が是の意を示す間もなく大きく開け放たれた。 「!」 一人の人影に、景麒は目を瞬いた。逆光を浴び、シルエットだけを濃く落とすその人物。先程まで夢で熱さを含んでいた瞼の奥からは熱が逃げていく。 そこに立っていたのは、武人 楓椿だった。 ::::: 黒髪をきっちりと結わえた背の高い彼をを景麒は表情を変えずに見据える。楓椿も、薄く開けた瞼の隙間から、その覗く黒眸に鈍い輝きを纏わせる。彼の薄い唇が歪み、生まれた隙間から声が漏れた。 「台輔、御機嫌麗しゅう。御目覚で御座いますか」 「無礼者!取次ぎ無しに台輔の御前に 翼を広げた芥瑚に、楓椿の弧を描く黒眉が跳ね上がった。 「ご無礼は百も承知。お初にお目にかかる、我が名は楓椿、以後お見知りおきを。私は主上からの命により、台輔より頂きたい物が有り、参上 「‥頂きたい物?」 表情を変えずに楓椿を見据える景麒。是 と答える楓椿の顔に浮いた笑みは濃さを増してゆく。 「貴方様が所持していらっしゃる筈の、珠翼 で御座います」 「‥?珠翼…?」 石像のように動かない、無表情の顔立ちの中に曇を掛けていく景麒に、楓椿は更に畳みかける。その視線は景麒ではなく、彼の胸元に垂れ下がる一つの宝玉に注ぎ込まれていた。視線を逸らすことなく、楓椿は唇だけを動かす。 「そう、簡潔に言えば、貴方の大切な方から頂いた物など‥。それを私にお渡し頂ければ‥私は直ぐにでもこの場から御暇させて頂きます」 「何をふざけたことを‥!」 空間に細い緊張が張られていく。芥瑚の顔が険しくなっていく中、景麒は彼女の前に腕を出し、 「静まれ、芥瑚」 「台輔‥!」 表情の起伏が見られない声音に、芥瑚は主を振り返る。だが、白い顎を引く景麒の目付きは、先程よりも幾何か鋭さを帯びていた。慎重に口内に言葉を含ませながら、景麒は練った言の葉を紡ぐ。 「生憎だが‥漢轍殿から何かを頂いた覚えなど無いのだが‥渡せる物など私には思い浮かばぬ」 沈黙を纏わせたまま、景麒の言葉を耳に受けていた楓椿。景麒を見据える彼の片方の黒眉が上がった。口端が上がり、喉の奥から震わせるような低音を響かせる。 「‥ほう‥流石は台輔。 「…」 「ですが台輔…残念ながら私はもう頂く物の目星を持ってこちらに参上しているのです‥」 薄く細く張られていた緊張が、濃度を増して分厚くなってゆく。 すっと楓椿の視線が景麒の顔から滑り落ち、胸元に留まった。 ただ、一点、紺青の薄闇の中、景麒の胸で眩しい程の煌きを零す翡翠の宝玉に。 楓椿の瞳が――光で濡れる。 「そう‥台輔が肌身離さず所持してらっしゃる‥その首元の物が、欲しいのです…」 静寂の中、見合う両者の間に張られていた緊張が――音を立てて切れた。 地を蹴り上げる力強い音共に、楓椿の瞳が狂気で燃えて、一飛で景麒との間合いを詰めに来る。翻る女怪の羽毛、影から次々と飛び出る景麒の使令の数々がその前に立ち塞がった。景麒は本能的に掌で首飾りを握り締めたまま、牀から転がり落ちるようにして床に降り立つ。巨大な両面開きの扉から打つかるようにして回廊に飛び出した。あっという間に染まる殺戮の混在する音が背後から轟き渡った。空気に飛ぶ鮮やかな赤。使令から吹き出した血の雫が珠となって四方に散っていく。 夢中で走りながら、景麒は自分の血の気が失せていくのを感じた。 (不味い‥!) 濃い臭気が鼻孔から入り込み、彼を内側から蝕んでいく。景麒から転変して逃げる力を奪う。視界を占める線が景麒の目の前でぶれ始め、撚り合わさっていく。景麒の風を切る速度が落ちていく。 そしてその時、扉が砕け散る太く高い金属音の混ざり合った轟音が、背後から響き渡った。 立ち上り膨らむ、白濁の砂煙の中から、突き抜くようにして飛び出す一人の人影。そしてその後から砂煙を砕いて続く使令の数々。走る楓椿が目の前を駆ける白金の煌きに向かって手を伸ばした。毛先に指先が‥触れる。 「台輔!!!」 悲鳴じみた声が背後でするのを耳に聞きながら、景麒は鬣から強い衝撃を感じた。それは鬣が根本から引き抜かれるような強い痛みと―その痛みに勝る臭気。 「…!!」 バランスを崩し、床にしたたかに身体を打ち付けた景麒は声もなく悶絶した。楓椿は景麒を掴みながら、口元に完璧な弧を描く。 「私から逃げられる筈が無いでしょう?」 「‥!」 景麒は腹から込み上がる吐き気に口元を抑えた。景麒の意識が揺らぐ中、楓椿は背後で唸る使令達に顔を向ける。その中の一匹、班渠に焦点を当て、楓椿は目を細めた。楓椿は血に濡れた刃を照らつかせ、景麒の首元にあてがう。 「お前たちも今動けば主人がどうなるかぐらいの分別は有るな?お前たちの大切なご主人は今、血に酔っておられるのだから、下手に近づかない方が彼のためだ…」 背後で芥瑚が顔に両手を当てる中、班渠は喉奥から低く唸った。楓椿は薄く笑い、既に意識の無い麒麟に近寄る。だが景麒から首飾りを外そうとした瞬間、ピクリと楓椿の片眉が跳ね上がる。景麒の指は、意識をなくしても尚首飾りをきつく掴んで放さなかった。楓椿が外そうとしても、決して外れない。楓椿は溜息を落とす。 「そうまでして渡されたくありませんか…」 ならば、と楓椿は顎を煽る。 「あなたごとお運びするまでです」 景麒は何も応えない。椿楓はぐったりとした彼を肩に抱え上げた。景麒の金糸が音もなく肩から滑り落ち、地面に着くか着かないかの場所で止まる。使令が影に溶け込んだのを確認した楓椿は、笑いながらその場を去ろうと足を踏み出した。足音だけが響く回廊には、地面から持ち上がり始めた月が光を斜めに差し込ませ始め、重なった輪郭は闇の奥に消えていく。 意識のない景麒の鬣だけが、淡く月影を弾いて――揺れていた。 ::::: ―その時、ふとした何かの気配を追うように、祥瓊は夜の香りに顔を向けた。 祥瓊は、一人誰もいない金波宮の庭園の欄干に、その身体を凭せかけていた。草木の頭同士が、流れてこすれ合う音は耳には優しい。庭園に吹き抜ける風は極寒の肌寒さから、 風脚だけが早くて、月から引き剥がされた雲の衣は風に揉まれて闇に消えていく。 その光景に目を細めながら、祥瓊は緩慢な吐息を唇から零した。心にも、今 上空で吹き荒れる雲の衣が張られているような錯覚に、祥瓊は眉根を寄せる。心にへばり付く、厚さと薄さが撚り合わさった雲衣は、祥瓊の心に輝いている筈の光を覆い隠してしまっていた。 風に洗われ、一瞬僅かに顔を出した透ける白色は紺青の髪を照らしていく。祥瓊は自身の、 そこに立っていたのは、祥瓊と同じように月明かりに髪を濡らす、一人の黒髪の少女だった。 月にまた雲の布が絡まり、光は薄く、目の前の少女の顔に影を落としていく。先日遠征から戻ってきたばかりの友を、祥瓊は瞬きしてその姿を目に入れた。 「鈴…?」 少女―鈴は何も答えない。 「鈴?どうしてこんな所に…」 彼女の黒髪が、風に流れていく。とっぷりと暮れた暗さが辺りを満たす中、鈴は無言のまま、強い眸で祥瓊を見つめていた。そのいつもと違う様子に祥瓊は不思議そうに首を傾げる。遠征に行くまで、この友の態度はいつもと同じ筈だった。けれど、帰ってきてから、鈴は何かが変わっていた。 ―何が、あったというのだろう… 「す…」 緩い風が吹き抜ける。 もう一度、祥瓊が名を呼ぼうとしたその瞬間―鈴は顔を持ち上げ、強い声を放った。 「祥瓊」 「‥?」 上空から、雲を落とした月明かりが流れこむ。 光の帯が鈴の顔を照らし、彼女の顔立ちの陰翳を濃く刻んでいく。祥瓊は思わず息を呑んだ。 それは鈴の瞳はあまりにも透明で、誰にも屈しない力強い意思を湛えていたから。 微塵も視線を逸らすこと無く、鈴は目の前の少女の瞳を見つめる。その唇だけが祥瓊に向かって強い言葉を放った。 「大切な話があるの」 祥瓊は言葉も発せられず、鈴を見つめる。 戸惑うように視線を揺らす一人の少女と、対照的に決して揺らがない視線の一人の少女。空中で、二つの視線が打つかるその瞬間――一陣の風が鋭さを持って吹き荒れた。 |
| back index next |