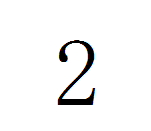 |
|
酷い喧嘩をした。喧嘩をしたことも無かった自分が。些細な一言だったのだ。心のささくれを引っ張り、破られた。血が、流れていった。 涙で滲んでぼやけた心の文字はもはや読めない。 少女を傷つけた本人が読まねばならなかった彼女の心の文字は、潤んで斑となって彼女自身にも読めなくなった。 だがそんなことはもはやどうでもよいことだった。 彼女の中では今、自分が酷い喧嘩をしたことも、自分がそれまで喧嘩をしたことも無かったことも、全て無かったことになっているのだから。自分が何もかもを奪われたことさえ、彼女は――知らない。 細い糸のような雨が少女の顔を叩いていた。音もなく空から滑り落ちる水滴は僅かの間肌にとどまり、また振り落ちてくる雨と溶け合って頬を流れ落ちていく。その繰り返しだった。 地面は雨に揉みほぐされている。体の周りをぬかるみ、ねっとりと柔らかい泥が溜まる。真紅の波が流れて、薄い水たまりの水面に華のように広がっていた。 少女は悪寒に震え身震いした。 体の奥から込み上げてくる寒気に歯の根が合わない。何とか唇でかろうじて蓋を被せるが、その内側で歯がこじれる。漏れる吐息は唇を離れた瞬間に白く凍りつき、それは霧となって目の前に広がった。 「…」 震えながら瞼を押し上げる少女の硝子の瞳に映る空は、どこまでも果てしなく濁って黒ずんでいる。虚無だ。よろめきながらも彼女はなんとか膝を着き体を泥から引きずり出した。 どれくらい時間が経ったのだろうか。 ――しばらくそうしていたのだろうが、不意に彼女の瞳の端に何かが映った気がした。暗く淀んだ色しかなかった彼女の世界に灯る、一点だけの仄かな明かりだった。 (光だ‥‥‥) ポツリと頭で自分の声が呟く。足を泥にめり込ませ、沈んだ足を引き抜くを繰り返しながら、真夏の光に群がる夜光虫のように少女は暖かな暖色の灯に向かっていく。いくらか歩いているうちにそれは一つではなく、小さな粒がいくらか寄り添うことで塊として成り立っていることに気が付いた。口から洩れる白い霧が機関車の汽笛のように彼女の存在を浮かび上がらせている。 進む 微かに声が風に乗って聞こえ、湿気臭い空気が肺を満たして吐き気がする。足が止まった時、光が何本かの松明であることに気が付いた。人影の被った蓑のようなものの一部が松明で照らされる。 体つきが違う大小様々な男たちだった。 背の高い者もいれば低い者もいる。松明が赤々と彼らの手元を赤く照らしていた。 その光景を見て彼女は立ち尽くす。そうしているうちに男たちのうち一人が暗闇の中、棒のように立ったままの人影に気がついた。 「おい、お前こんな所で一体何をしている?」 きょとんと少女は困惑したように男たちを見つめた。そんな彼女とは関係なしに翡翠の瞳の中で松明の光が楽しげに揺らめいていた。 顔に火の明かりを近づけられ仄かなぬくみが頬に広がる。暗闇の中彼女の整った顔が浮かび上がった。 男達は緊張を張り付けていたが、女だということと彼女の見目の良さに少々彼らの雰囲気が和らいだ。 「村の者では無いな‥。傘も無いのか?なぜこんな物騒な所を一人で歩いている?ここは未だ妖魔が出るという噂なんだが」 「よう‥ま?」 「そう 妖魔。お前のような娘なんぞ柔らかくて甘い絶好の餌だぞ」 「娘‥‥?」 少しだけ彼女の眉根が寄った。男たちは気づかず彼女の顔を覗き込む。さっきとは別の野太い男の声が闇に響く。 「とにかくこんな雨の中傘も差さずに一人で徘徊というのは感心できんな。どれ、村に連れて行ってやろうじゃないか。お前さんの名は?」 答えようとしたその時になって彼女は自分が何者か分からないことに気がついた。つい先ほど自分が女であることも分かっていなかったことを他人事のようにぼんやりと思い出す。 目が覚めた瞬間から、彼女の中には何一つとして残っていなかったのだ。 たった一つの自分の存在さえも。 ::::: そうかい、あんた大変だったねェ ここが何処かも分からないんだろ?とにかく入った入った。いつまでもそんな泥まみれじゃあべっぴんさんが台無しだ。 男たちに連れられて少女は小さな集落に立っていた。少女の真の名を陽子と言ったが本人はそのことを知らない。 連れてこられた集落は高さが4メートルほどのこぢんまりとした家々がが集まっただけのような場所だった。 小さな窓から家々の中の明かりが漏れ出て、その部分だけが四角く雨を照らしだし闇夜に浮かび上がらせていた。今たどり着いた一軒の家の前で、陽子はこの家の家主らしい一人の女に肩を叩かれている。 促されるまま中に入ると中は明るい光で満たされていた。夜目に慣れた目が反射的に窄まり、かんかんとした光を吸い込んだ眼が慣れた時、家主の女が話していた男たちを見送り閂を下ろす音がした。陽子を振り返った女が笑う。 「さぁ 不運な御嬢さんに恵んでやれるような物じゃ無いかもしれないが、何か食べなきゃ体が持たないよ」 そう言った女は陽子を座らせ掛かっていた鍋に火を灯す。初めは湿気ていた木が火種に侵されぷすぷすと煙を上げ始める。やがて鍋の底を舐めまわすほど火が育つ頃には部屋はとっぷりとした温かさに包まれていた。 温まったスープのような汁物を出してくれ、陽子は女を見上げる。 「これ‥‥」 「あんたのために温めなおしたんだ。飲んでおくれ」 笑う女の顔は朗らかだった。一瞬戸惑いながら恐る恐る汁物に口づける。熱い液体が口内に染み渡り、溶けるように体に入っていたそれに思わず陽子は溜息を洩らした。 「美味しい‥」 「そりゃそうさ。材料こそ痩せて貧相かもしれないが、この私が作った料理が不味いはずあるもんか」 思わず顔を上げた。目の前の女の服は擦り切れ手は固く節々が浮いていた。この集落、家々が粗末な作りだったことが彼女の頭を過る。 「ここでは‥作物は取れないんですか?」 「予王が崩じて以来新しい王が発ったんだが、ここには未だ妖魔が出るし土地も痩せ細っているのが実情だね。だがまあ、今度の王は男王らしいから少しはこれから期待が持てそうだ」 「男王?」 聞きなれない響きに語尾が上がる。ああと女は言った後あからさまに顔を顰めた。酷い汚物を見た後のような顔だった。 「女王は駄目だ。この国は女王運に恵まれていないからね。先の女王が良い例だ。出来れば私が生きているうちは女王は願い下げだねェ」 「女王は駄目‥‥」 「まぁ駄目と決まった訳じゃないが少なくとも慶に良い女王というのは聞かない話だ。恭では女王の方が良いと言われいるが‥。現在の供王君はもう九十年の治世をなされているらしいがね。男王である達王がこの慶では賢帝だった。」 「この国々には王がいる‥‥」 「そうだ。王が居なけりゃ国は荒れる。そして王が道を踏み外しても国は傾いていくもんさ。」 国の重大な柱だねと女は着いた肘の手の平に頬を乗せた。憂鬱そうな色を帯びた視線は明後日の方を向いていて、王というものは自らの民にこんな顔をさせているのかと陽子は苦い気持ちを感じた。 仕組みは理解できる。少女陽子に欠落しているのは自分という概念だけであって、物を見、考え理解するということに関しての弊害は見られなかった。 だが今の彼女にとってこの話は擦り硝子の向こう側の話であることに変わりはない。 自分の内側に目を向けてみたがそこには群青色の無表情な海があるだけだった。生命も何もない、ただ色を帯びた塩水だけが彼女を満たしている。 ふいに口内に塩辛さを覚え思ったことが口から零れた。 「そんな大事な人を誰が決めているんですか?」 そりゃあ‥と女は陽子を見つめる。陽子も返すように彼女を見つめ返した。見つめる少女の何も残っていない澄んだ瞳がきょとんと煌めいていた。 「麒麟だよ。一国に一しかいない神獣さ。」 「き‥りん‥」 きりん?ずく と心のどこかが波打った。穏やかな自分の中の海がそこだけ海底から揺さぶられる感覚だ。思わずその海を振り返るが何もない。緩やかな 「そうさ。だが麒麟なんてとうていお目にかかれるようなもんじゃないよ。この慶では景台舗がそうだね。先の予王の時はどうなることかと思ったが、今度こそ見込みのある男王を選ばれた。本当に良かったよ」 「そう‥ですか‥‥」 心に何か 少しだけ眉根を寄せて何か物思いにふける彼女に女は笑った。 「なあにそんなに難しい話じゃないさ。麒麟も王も私にもあんたにも遠い遠い雲の上の話さ。まあ今はそんなどうにもままならないことはほっといて、とにかくあんたの身元を調べるのが最優先かね。自分の名も分からないなんて不便だろう?体を休めている間に役所に出されている探し人の文献を調べてみるよ。湯を張ってあげるから湯浴みをしな」 ありがとうございます とのろのろと彼女は礼を言った。自分の名も分からないという事態を思い出して苦笑する。 女は一声笑うと水を盥に張り湯を沸かし始め、粗末な粗い着物の裾が石とすれ合う音がした。少女陽子の中の自分史は真っ新の美しい紙のようだった。鉛筆のなぞった線さえも見えないそのページに彼女はため息をつく。その間女はこれは駄目だ、これは小さいなどと口の中で呟きながらの替えの着物を一揃い揃え上げた。 「今のあんたにはちょっと地味かもしれないが‥‥」 「そんな!十分です。ありがとうございます」 女は湯気の立つ盥を運搬用の押し車に乗せると陽子を手招きする。湯面がゆらゆら揺れて陽子の顔を映しては歪ませ湯気で曇らせていた。招かれるままに陽子は部屋に入り着替えを受け取る。 「あの‥何から何まで有難うございます」 頭を垂れる陽子を見、後ろ手に扉を閉めながら女は笑う。 「なぁに大したことじゃあないさ。人はみんな天帝の子。困った時はお互い様さね」 ふわりと陽子は安心したように笑い、向きを変え着替えを始めようと着物の襟に手を掛ける。 穏やかな湯けむりが満たす柔らかな霧の空間に、衣の払われる音だけが微かに響いて跡を残していく。 その時、重たい木の扉が軋み閉まる微かな物音を耳に入れながらも、陽子は扉を閉めていく女の顔にまで目を向けていなかった。 陽子が目を離した瞬間に変わった、張り付けていた物柔らかな笑顔を剥いだ後の無表情に。 湯気が籠り始めた室内は蒸し暑く白み始めていた。 ふと過ぎ去ったものを思うように細められた陽子の目に家の中に潜り込んだ幾つかの影は映らない。陽子は湯を見つめながら衣を体から払う。 自分という空白の存在。空白になった陽子の中の物は全て洗い流されていて、それが良いことなのか悪いことなのかどうかということさえ今の彼女には推し量ることは不可能だった。 |
| back index next |