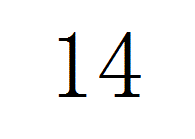 |
|
back index next 水を打ったように静かになった眼下は人という人で埋め尽くされている。だが足元から見上げてくる顔の群れ群れに陽子は微塵も興味を抱いてはいなかった。風が顔を吹き付け、舐めていく中、砂塵だけが目の前を霞ませる。 陽子は空を振り仰ぎ、上空から流れこむ光に目を閉じた。陽子の心の中に渦巻くのは疑念と疲れ、煩わしさと微かな悲哀感、そして胸の奥から噴きあげてくる怒りだ。そして同時に彼女の頭を占めていたのは、先程から蓄積していく遊蘭の発言の数々だった。この淡い緑の巻き毛の娘に、陽子はどんな感情を持っているのかうまく説明できなかった。もやもやと霧のようにその不快感が広がり、なんと形容して良いのか分からない。陽子はむず痒さに眉根を寄せた。 塀の上に佇む一人の少女を、周りの者は呆然とその姿を見つめていた。あれが‥あの薄汚い少年だろうか。明らかに彼女自身の意思を湛えたその瞳は力強い光を湛えている。 そして何よりも圧倒されるのは 彼女から発せられる尋常ではない覇気だった。 陽子の瞳が遊蘭に向けられた。ゆっくりと陽子の瞳が細められる。 覇気を湛えた翡翠の輝きが遊蘭をまっすぐに射抜いていた。未だ尚暴言を吐こうとしていた遊蘭は、その覇気に思わず口を噤んだ。陽子は冷えた眸のまま言の葉を紡ぐ。 「人は…誰の奴隷でも無い。そんなことのために…生まれてくるんじゃない」 自分が話している言葉がまるで他人が話している言葉のようだ。無感動に陽子は感じる、自分が発したそれはどこかで知っているしらべだった。言葉は同じ雫を落とし、同じ波紋を広げていくような錯覚を起こさせる。だが今の陽子には酷くどうでもいいことのように思われた。 陽子が静かに瞳を揺らす。砂埃が舞い、低く流れ出る覇気に押された遊蘭は思わず気圧され一歩下がった。 「なぜ、王であるという者が、人と人との間に序列があることを容認する。人と人との段差を認める。弱者が踏みにじられることを許す」 低い低い声が大地を這った。冷えたその翡翠の瞳の奥に閉じ込められた遊蘭は表情を変えることも出来ないまま、苦し紛れに吐き捨てるように叫んだ。 「権威なんて…そんな物じゃない!それがなきゃ世の中なんて回って行かないわよ!」 その瞬間、あぁ、と陽子は遊蘭に対しての感情の正体を理解した。霧が晴れるように、それはあらわになる。そうか、この感情は―― 侮蔑だ。この娘は、愚かだ。 差別的な思想を当然のように振りかざすこの娘に、敵愾心を抱く気概すら持とうと思えない。知りたくなかった嫌な感情を陽子は受け止めた。そして静かに遊蘭を鋭い視線で見つめた。 「そうだな…天は世界に権威を与えた。代償と共に。貴方は何も分かっていない。権威に伴うは責任。権威のない弱いものを導くという責任だ。だからこそ、その器量と力量を認め、そうなろうと努力する者の姿に敬意を表し人は頭を垂れる。何もなしに人が頭を下げるものか。そんなこともあなたは理解出来ないのか」 そう、だからこその権威なのだ。それは同時に重い足かせを嵌められる事と変わりはない。それを理解した上でその重い衣を纏う者はどれほどいるのだろうか。 「弱者を虐げることは世の理の中、当たり前のことだとあなたは言った」 天はそのように人を差別させるために、一部の者に甘い汁を吸わせるために、王に民を預けるものなのか。命を預ける、ものなのか。 しん と暖色の光にそぐわないほど冷えた空間に言葉が反響する。誰も彼もが、気圧されて口を開くことが出来なかった。その場を圧倒するような、覇気が大気を震わせる。人はひしめくようにその場にいたのに、誰も動くものはいなかった。陽子の唇から怒りを孕んだ声が流れる。 「それが己の民全て担った王の言葉か」 「自分こそが王だと名乗る者の言葉か」 碧の翡翠が燃え上がる。次の瞬間、雷鳴のように声が響き渡った。 「答えろ!!!!」 ひっとどこかから、誰かから漏れた音が響いた。陽子の覇気に圧倒された遊蘭は、冷水を引っ掛けられたように一言も発することが出来ないまま、地面に尻餅をついた。言葉も無く、彼女は口をぱくぱくと開け閉めする。 視線を泳がせる中、ある一つの物が遊蘭の目に留まった。 それは光に照らされその形を美しさをさらけ出している陽子の剣。ひっきりなしに遊蘭は瞬きを繰り返しながらそれを目で確認する。その形、その装飾、そしてそれに垂れ下がるとろりと碧い玉。 遊蘭は自分の呼吸が速くなっていくのが分かった。緩やかに不安は這い昇っていく。昔こっそり父親の書庫から持ちだした物が彼女の頭を過り形を浮かべた。父親は県庁に太く繋がっている人物だったから、それは彼のもとにひっそりと流れてきたのだ。 父は持っていても、こんなところには絶対に流れ着くことは無いから意味はないのかもしれないと苦笑いしていたが、自分こそは王になるものとばかり思っていた遊蘭には願っても無い物だった。 慶国宝重の図面 それを持ち出し、いつか本物を自分の身の回りに置くのだとうっとりと眺めた物だった。遊蘭は顔から血の気が下がっていくのを直に、感じる。 記されていた物に酷似しているあれは‥目の前に居る紅の髪の娘が従わせていたあの―剣は‥!あの…玉は! 慶国の宝重 水禺刀 と 碧双珠 徐々に霞んでいた形から、輪郭を型取り始める真実。 その 宝重を従わせることが出来た陽光は‥!! 空気をつんざくような甲高い悲鳴が遊蘭の口から飛び出した。瞬間、体中の全ての血が流れ出たような心地が遊蘭の背筋を駆け抜けた。周りが狼狽える中、遊蘭は ―陽子に向かって深く深く頭を下げた。 地面と額を合わせ紅髪の少女に叩頭する主には周りに衝撃を走らせた。なぜ、そうするのか その理由は今の彼らには分からない。 そして それは今の陽子にも分からなかった。 陽子は薄く眉を潜める。一瞬の時を越えて、楓椿が飛び上がった。振り下ろされる白刃を陽子は崩れかけた石壁の上で受け止める。不安定な足場に亀裂が走る音がした。 陽子は目の前の女兵士の様子が違うことに眉間の皺を深くする。女兵士 楓椿の瞳が開かれ、陽子の顔をじっと食い付くように見つめた。光を弾いて濃い赤を帯びた髪を、深い緑の瞳を、見つめる。 その眸が――恍惚の色を浮かべ、熱を帯びていることに…陽子は微塵も気が付きはしなかった。 武人の先程とは違う様子に、一瞬怪訝そうに顔を曇らせた陽子だが、目の前に居る女に―ある決定的なことを感づいた。その視線が楓椿の剣の柄から伸びる腕の輪郭をなぞり、力の籠もる筋肉の塊を捕らえる。そして眸を持ち上げた陽子は視野に収まりきらない程の、異様に背の高いその兵士を見つめ薄く目を細める。 陽子は目の前の白刃を振るう人物をひたと視線で射ぬき、囁いた。 「お前…男だな?」 楓椿の顔に一瞬衝撃のようなものが走った。そして、その顔にゆっくりと含んだ笑みが浮かぶ。口端を彼女、いや、彼は釣り上げた。 「なぜ…見抜かれた?」 「こんな力の女がいるか」 陽子の青刃が走り眼の前の刃をはじき飛ばした。一瞬の力の緩みを弾かれた楓椿の体躯が傾き、空中でバランスが崩れていく。高く高く弾かれた剣は空中で弧を描きながら地面に深々と刺さり、剣の柄が地面から突き出る形となった。 (強い…!) 楓椿は自分が剣を弾かれたことに驚嘆の意を隠せない。だが、楓椿が地面へと引きずられていくのを見た陽子は、もう視線を彼から外していた。陽子のその視線は眼下を一度だけ見下ろして玉葉に向けられる。 握りすぎて白くなった手をした娘にそっと陽子は微笑んだ。玉葉は、叩頭せねばと手のひらを地面につこうとする。湯屋の娘 遊蘭が礼をしている理由が分かるのは彼女だけだった。 だが 陽子はそれを手で制し、玉葉に向かって――頭を垂れた。 玉葉の瞳が大きく開かれる。驚愕で言葉も出ない。その瞳に映った赤い髪の少女の口が ありがとう、世話になった と動く姿を最後に、彼女は剣を鞘におさめて、大木に飛び乗った。気配は一瞬で掻き消えていく。 枝が揺れる音がして、やがてその音は小さく聞こえなくなっていった。 ::::: 静寂のなか、体を起こした楓椿が地面から立ち上がる。消えた人影を目で追う、その瞳にうつっていたのは熱を帯びた陶酔だった。 「なんと…お美しいお方」 光のなかに現れた美しい少女。なびく緋色の髪が光を散らし、碧の瞳の輝く色彩が彼を捕らえていた。気怠げな微睡みがうって変わり、瞳が燃え上がり口端がゆっくりと上がる。 「殺してしまうなどなんと勿体ないことか。あの方は私が手に入れる…!」 その言葉は誰に届くこともなく、楓椿の口の中で甘い味を残していった。 陽子は立ち去った後のその場で、何が起きたのかを知る術は無い。その場に居た一人の人間を執心させたことも、彼女に出会えたことに感謝していた人間がいたことも。楓椿の眸が熱を帯びているその傍ら、人垣が呆然と立ちすくんでいるなか、一人の少女が深く頭を垂れていたことも陽子は知らない。 いずれ、この湯屋で駆け巡るだろうその真実は、その場に居る者を驚愕させ、そしてまたある者を戦慄させ、そして今起こった場面を見た人々を納得させるだろう。 だが、それはもう少しだけ後の話になる。 今、何も知らない人々の群れの中心で風が揺れる。そんな中で玉葉は少女の消えた方角に向かって深く深く叩頭する。自分と関わってくれた、去っていった彼女に願いと希望と謝礼を込めた。 玉葉は小さく呟いた。 「どうか…御無事で ――――」 最後の言葉は、木々のざわめきに掻き消されていった。 一人の少女が飛び乗った衝撃で、枝だけが静かに、揺れていた。 |
| back index next |